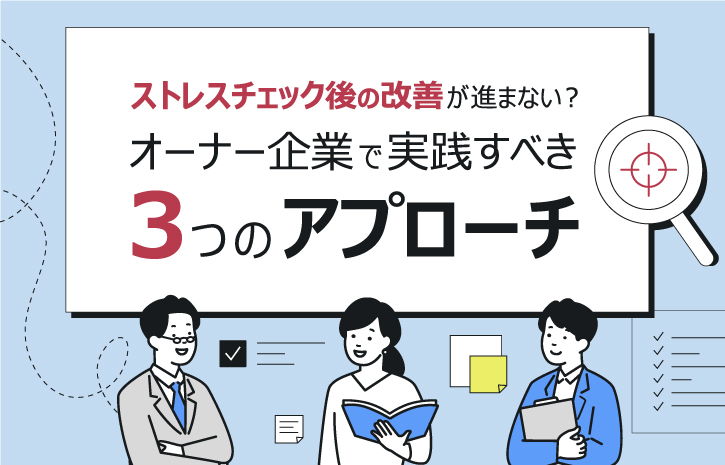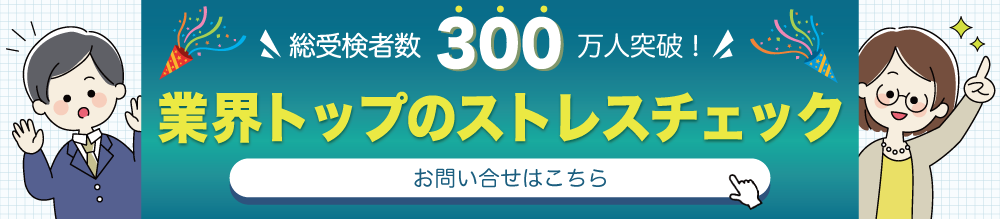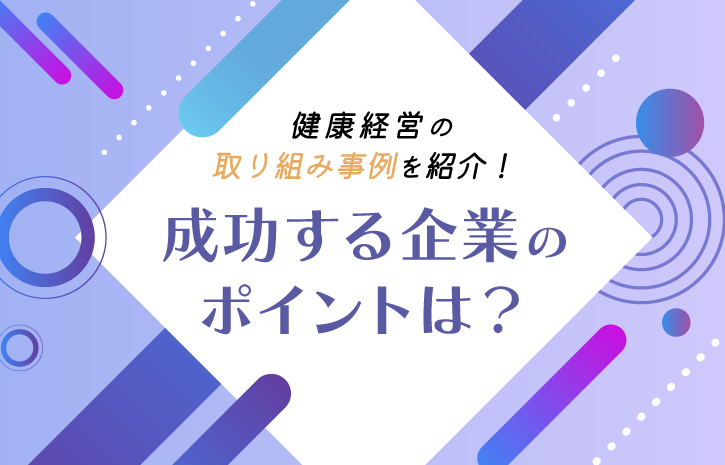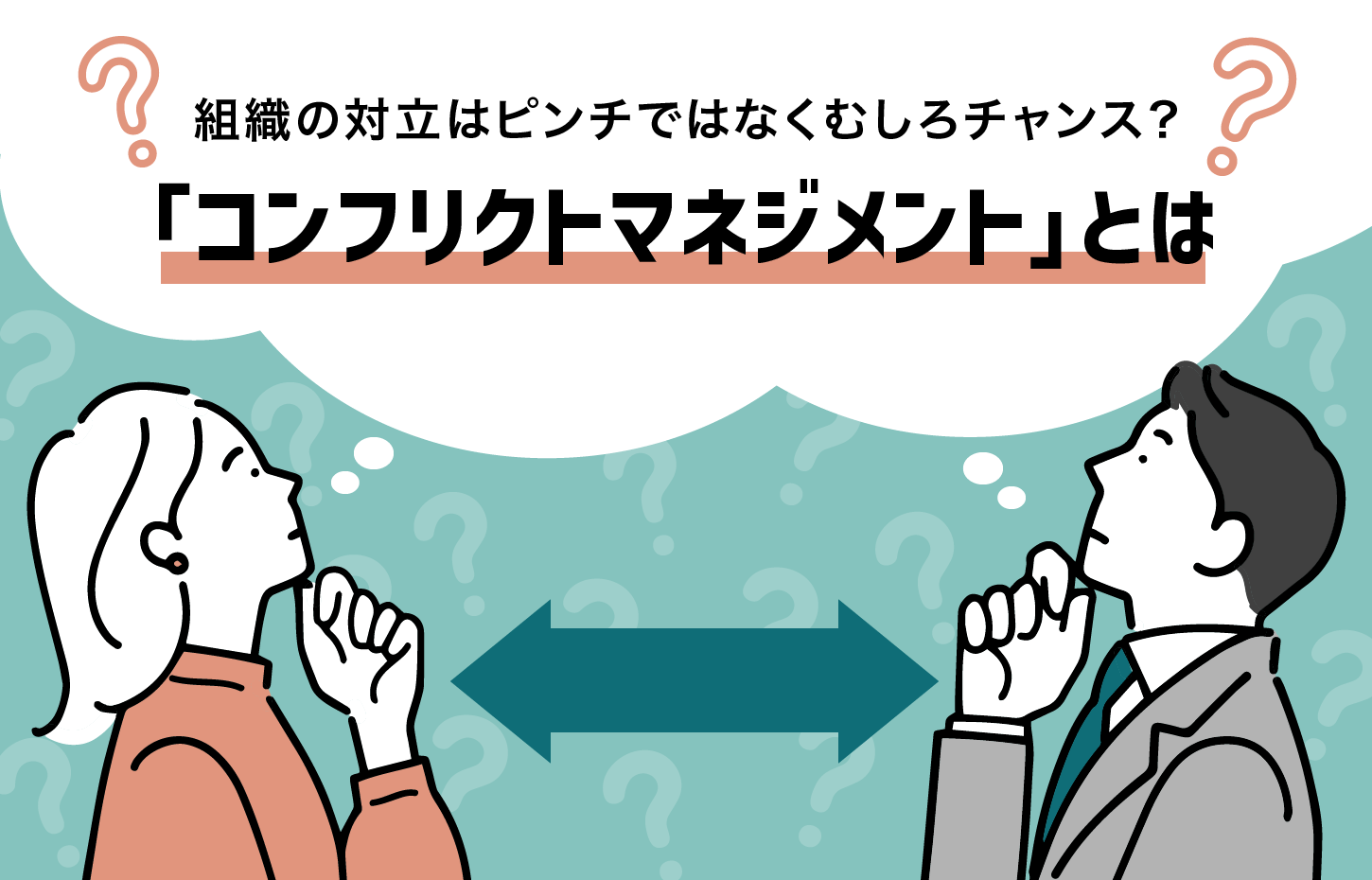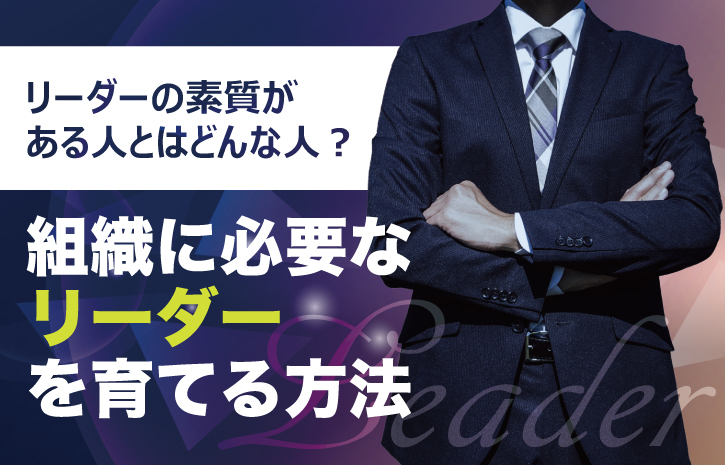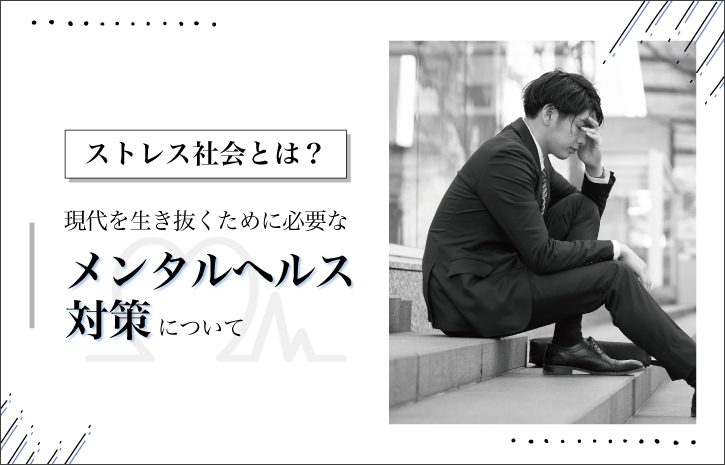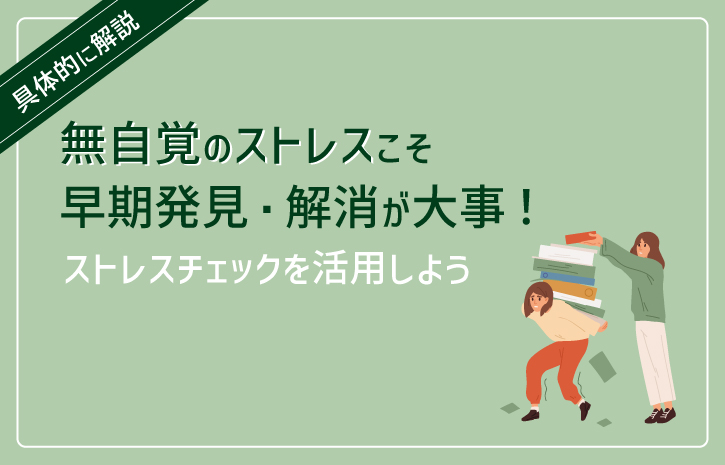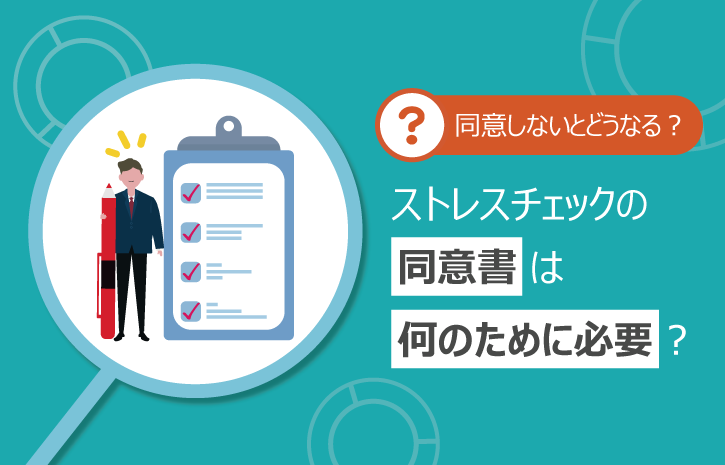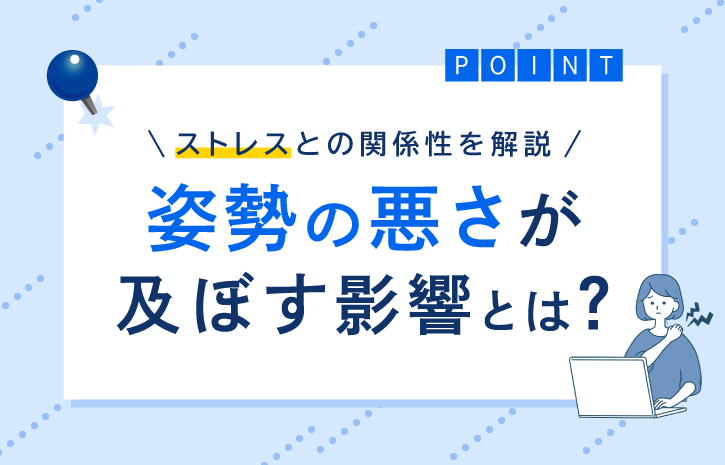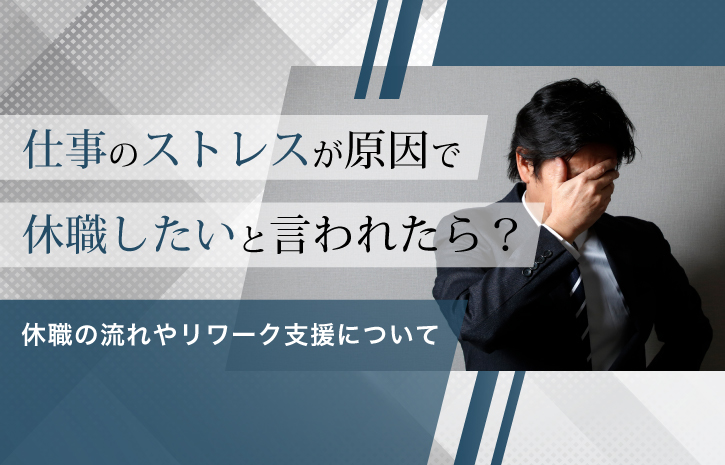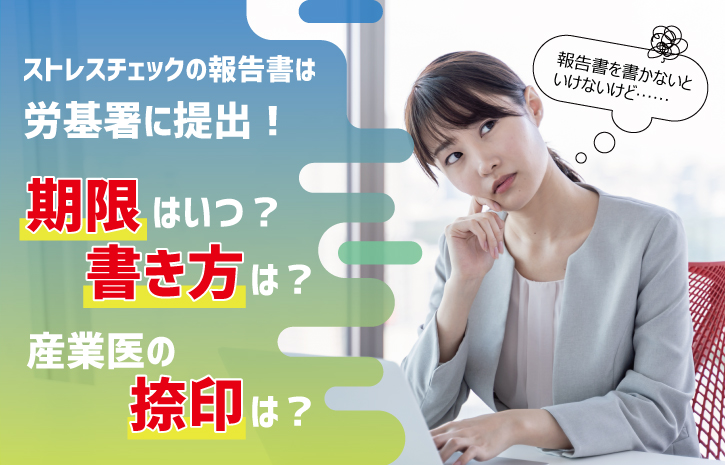「ストレスチェックで高ストレス者が多いのに、経営者が改善に動いてくれない」
「改善提案を出しても『今までこれでやってきた』と却下される」
オーナー企業の労務担当者なら、一度はこんな壁にぶつかったことがあるのではないでしょうか。
オーナー企業での職場環境改善が難しい理由、それは経営者と所有者が同一であるという構造にあります。
この特殊な環境下で、労務担当者が前向きな変化をもたらすための3つのアプローチをお伝えします。
なぜオーナー企業ではストレスチェック後の改善が進まないのか
オーナー企業では、経営者の価値観や個人の意向が、会社の文化や方針に極めて強く反映されます。
労務担当者がどんなにデータや論理に基づいて改善の必要性を訴えても、オーナーの「これで今までやってきた」「自分のやり方が正しい」といった強い信念や感情的な抵抗に直面しがちです。
また、非オーナー経営の企業と異なり、株主や取締役会といった外部からのチェック機能が働きにくいため、環境問題が顕在化しても、オーナー自身がそれを問題と認識しない限り、抜本的な解決には至りにくい傾向があります。
さらに、オーナーのトップダウンの意思決定が絶対的であり、従業員の声やボトムアップの提案が軽視されやすい風土があることも、改善を阻む大きな要因です。
オーナーを動かす3つのアプローチ
労務担当者として、この壁に挑むためには、戦い方を変える必要があります。
感情論や正論だけでなく、オーナーが最も関心を寄せる「経営的な視点」、すなわち「カネとヒト」に焦点を当てたアプローチを取りましょう。
アプローチ1:データとコスト削減効果でオーナーを説得する
改善提案を「従業員のための福利厚生」としてではなく、「企業のリスク回避と利益向上」のための投資として位置づけます。
離職率の定量化
過去の離職者にかかった採用コストと教育コストを算出し、「この環境が続くと、年間でこれだけの損失が出る」と具体的な金額で示します。
生産性低下との関連付け
長時間労働やハラスメントによるメンタルヘルスの不調が、どの程度残業代増加や業務効率の低下につながっているかを示唆します。
法令遵守リスク
労働基準法などの法令違反リスクを指摘し、「罰則や訴訟によるブランドイメージ低下と金銭的な損害」という形で、オーナーにとっての最悪のシナリオを具体的に伝えます。
アプローチ2:スモールスタートで成果を実証する
最初から大規模な制度改革を提案するのではなく、コストが低く、短期間で効果が出やすい分野から改善を始めましょう。
たとえば、部門限定での試験的なフレックスタイム導入や、業務効率化のためのITツール導入などです。
その小さな成功体験をデータ(例:残業時間が○%減少、高ストレス者が△%減少)とともにオーナーに報告し、これは成功する投資であるという認識を徐々に植え付けます。
アプローチ3:信頼できる社内協力者を味方につける
一人で戦わず、オーナーに近しい信頼できる幹部や、現場で影響力のあるベテラン社員を味方につけましょう。
彼らがオーナーに対し「現場が変わり始めている」「効果が出ている」と進言することで、あなたの提案が受け入れられやすくなります。
職場環境改善はマラソンのようなものです。
オーナーの意識が変わるまでには時間がかかることを理解し、粘り強く、感情的にならず、データという客観的な武器を使い続けることが成功への鍵となります。
労務担当者として、あなたの努力は必ず現場の社員に届いています。
その熱意と論理で、一歩ずつ変革を進めていきましょう。
よくある質問(Q&A)
1:オーナー企業でストレスチェック後の改善が進まない理由は?
A: オーナー企業では経営者と所有者が同一であるため、経営者の個人的な価値観が会社の方針に強く反映されます。株主や取締役会といった外部チェック機能が働きにくく、オーナー自身が問題と認識しない限り改善が進みにくい構造になっています。また、トップダウンの意思決定が絶対的で、従業員の声が軽視されやすい風土も改善を阻む要因です。
Q2:オーナー企業で職場環境改善を成功させるには何が必要?
A: 感情論や正論ではなく、オーナーが関心を持つ「経営的視点」からアプローチすることが重要です。具体的には、①データとコスト削減効果を定量的に示す、②小規模な改善から始めて成果を実証する、③オーナーに近い幹部や影響力のある社員を味方につける、という3つのアプローチが効果的です。
Q3:オーナーを説得するために労務担当者がすべきことは?
A: 改善提案を「従業員のための福利厚生」ではなく、「企業のリスク回避と利益向上のための投資」として位置づけることが重要です。離職によるコスト損失、生産性低下による残業代増加、法令違反による罰則リスクなどを具体的な金額で示し、改善がビジネス上の利益につながることを論理的に説明しましょう。
Q4:ストレスチェックのデータをどう活用すれば改善につながる?
A: ストレスチェックの結果を、採用コストや離職率、残業時間などの経営指標と結びつけて提示することが効果的です。たとえば「高ストレス者率が高い部署の離職率は○%で、年間△万円の損失が発生している」といった形で、ストレスと経営損失の関連性を数値で示すことで、オーナーの意識を変えることができます。
Q5:小規模な改善から始めるメリットは?
A: 最初から大規模な制度改革を提案すると、コストや手間を理由に却下されやすくなります。部門限定のフレックスタイム導入やITツール導入など、低コストで短期間に効果が出る施策から始めることで、「残業時間が○%減少」「高ストレス者が△%減少」といった成功実績をオーナーに示すことができ、次の改善提案が受け入れられやすくなります。
Q6:社内協力者を確保する重要性とは?
A: 労務担当者が一人で改善を訴えても、オーナーとの信頼関係や影響力の差から提案が通りにくい場合があります。オーナーに近い幹部や現場で影響力のあるベテラン社員を味方につけることで、「現場が変わり始めている」「効果が出ている」という声がオーナーに届きやすくなり、改善提案の実現可能性が高まります。
Q7:オーナー企業の労務担当者が持つべき心構えは?
A: 職場環境改善は短距離走ではなくマラソンです。オーナーの意識が変わるまでには時間がかかることを理解し、感情的にならず、データという客観的な武器を使い続けることが重要です。粘り強く、論理的に、小さな成功を積み重ねていくことが、最終的な変革につながります。