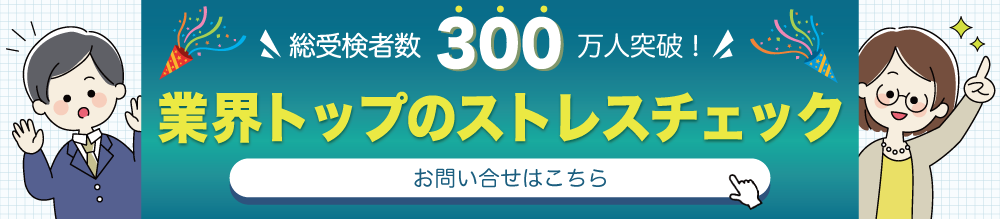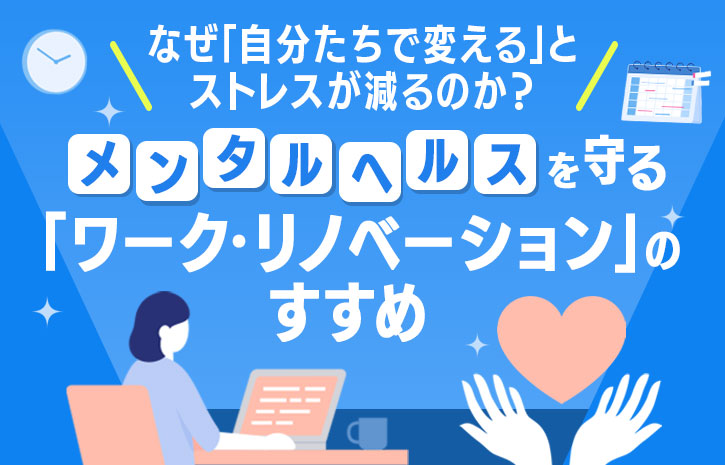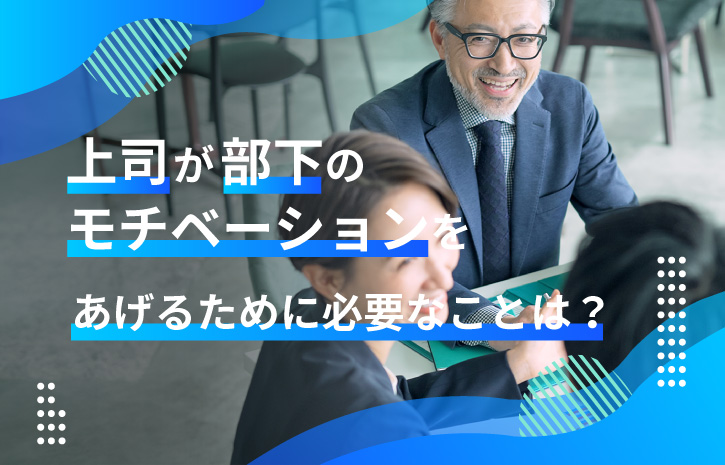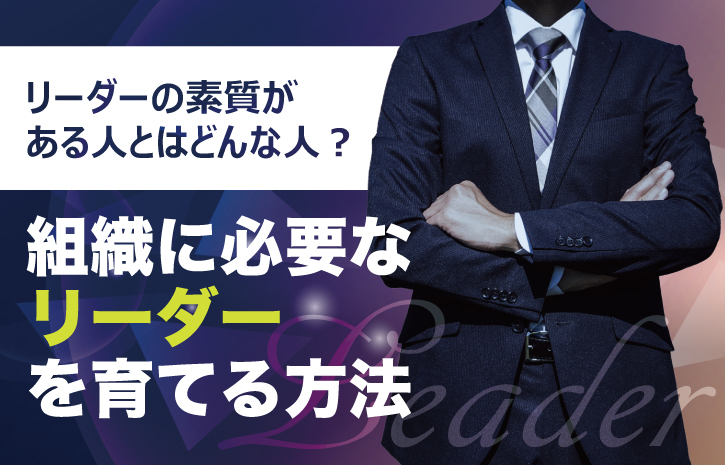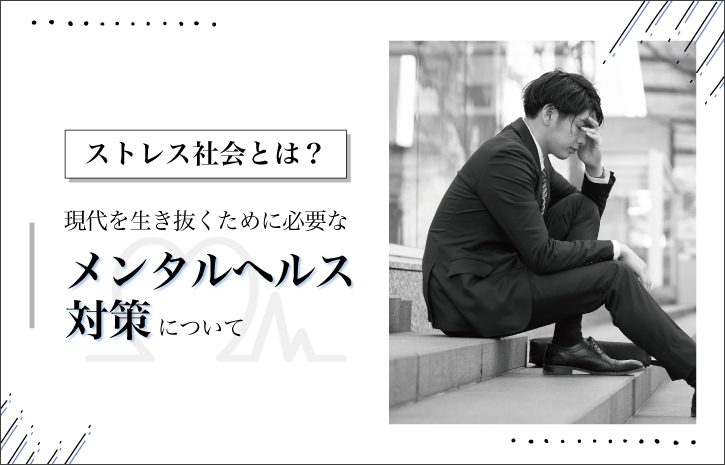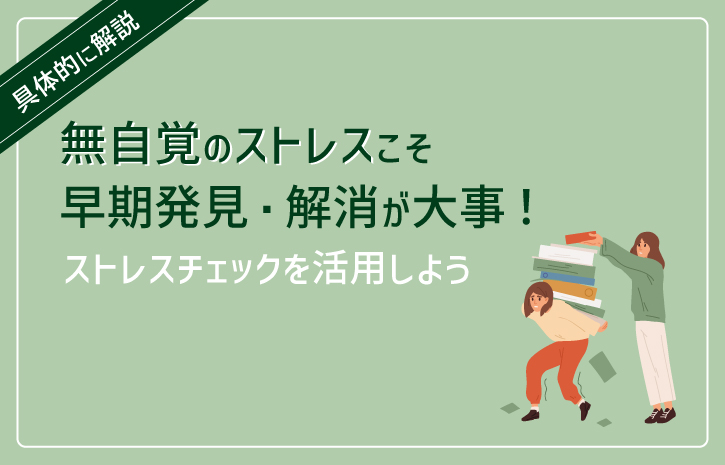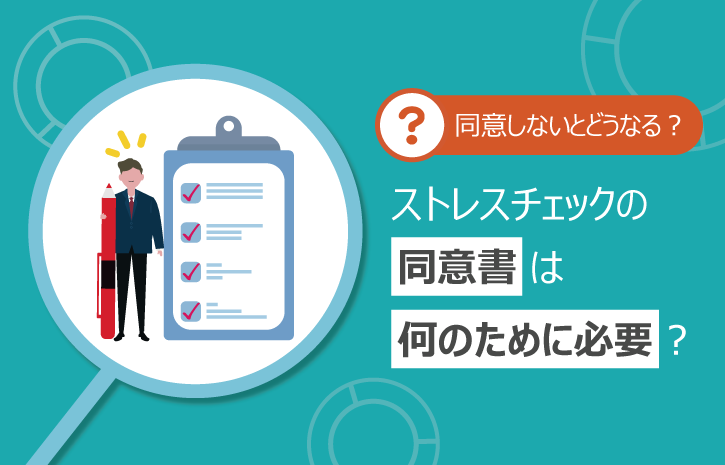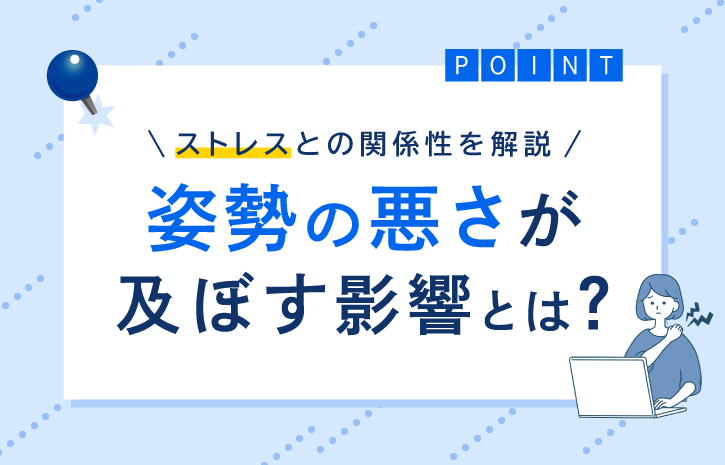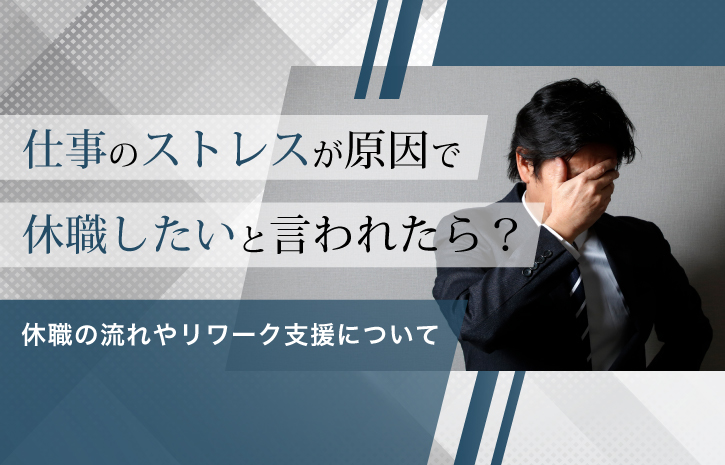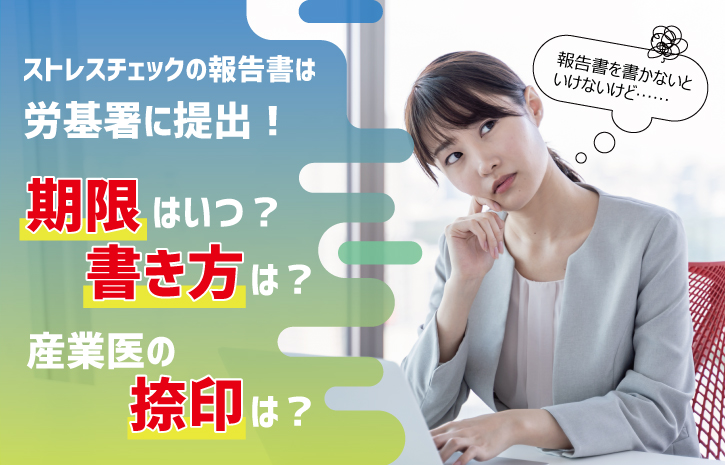職場内でパワハラ防止措置が取られてはいるものの「パワハラまではいかないが上司の言動が気になる」「態度や行動が感情的な上司に対してどう接してよいのかわからない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
本日は高圧的な上司の心情とそのような上司と上手く仕事をしていくために心得ておきたいことについて解説していきます。
高圧的な上司の特徴とは
高圧的な上司の具体的な特徴としては以下のものが挙げられます。
・感情的な言動をする
・立場・過去の成績を自慢する
・人によって態度が変わる
・言葉遣いが荒い
・言動が日によって変わる
高圧的な上司はなぜ生まれるのか
高圧的な上司とうまく働いていくためには上司の心情を把握することが重要な鍵となります。
上司が高圧的な態度をとってしまう背景をみていきましょう。
自分の考えが正だと思っている
過去の自分の実績や成功体験から、常に自分の意見を部下に押し付ける態度が高圧的だと思われてしまう。
過去に自分が上司に高圧的な態度をとられたことがある
自分がこれまで厳しい指導を受け、高圧的な上司のもとで仕事をしてきた経験から今の態度が普通だと思っている。もしくは、自身が苦しんだ経験を部下にぶつけている可能性がある。
自分に自信がない
弱さを悟られないように無意識のうちに強く見せているケースがある。
部下を成長させるために厳しい言葉を言う
厳しさは愛情であることを前提にあえて厳しい言葉で伝えている。上司と部下の間に信頼関係があると厳しい言葉も真摯に受け止められやすい。
ハラスメントの実態
2024年度にドクタートラストが実施したストレスチェックでは「職場でハラスメントを受けている」と回答した人の割合が5.5%でした(前年度5.7%)。
前年より改善しているものの依然として一定数の人がハラスメントを受けていると感じていることが伺えます。
また、厚生労働省が公表している職場のハラスメントに関する実態調査報告書では、過去3年間にパワーハラスメントに関する相談があったと回答した企業はおよそ6割に上ることが報告されています。
パワーハラスメントの行為者として挙げられたのは、「上司(役員以外)」(65.7%)が最も多く、次いで「会社の幹部(役員)」(24.7%)でした。
理想の上司を増やし働きやすい職場づくりを
理想の上司を増やしていくためには、会社として理想的な職場・上司の共通認識をもち、経営層が率先して情報発信していくことが必要です。
以下のように、現実的な方法でできることから意識してみましょう。
理想の上司像についての共通認識
「理想の上司とはどういった上司か」を社内で認識の擦り合わせをしましょう。
共通認識を持つことで、企業の実情に合った職場環境を目指すことができ、上司自身の意識付けにもつながります。社内の「行動基準」や「研修動画」などに反映させるのもよいでしょう。
経営層からの積極的な情報発信
経営層や上司から一貫したメッセージを出すことが非常に重要です。
なぜなら、組織として何を「良し」とするかが曖昧だと、現場での行動がバラつき、育成も評価も定着しないからです。
上司が部下を育成するための仕組みづくり
管理職向け研修(アンガーマネジメント、ハラスメント、傾聴スキル)を定期的に実施したり、部下からどう見られているかをアンケート形式で意見徴収したりするなど、上司自身が上司のあり方について考えるきっかけ作りを行うことが大切です。
まとめ
例年、およそ5%程度は継続的に「職場でハラスメントを受けている」と回答しています。
組織を成長させるためには、上司のあり方が極めて重要であり、上司が高圧的であると社員のモチベーションや生産性の低下につながります。そのため、社内で理想的な上司像を共通化し、上司自身がどうあるべきなのかを考える機会を設けることが大切です。
一度の対策で終わらせず、継続的に改善、新たな施策を導入しながら信頼される組織文化をつくっていきましょう。
<参考>
・厚生労働省「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」
よくある質問(FAQ)
Q1. 高圧的な上司の特徴とは何ですか?
A. 高圧的な上司の特徴として、感情的な言動をする、立場や過去の成績を自慢する、人によって態度が変わる、言葉遣いが荒い、言動が日によって変わる、などが挙げられます。これらの行動は、部下にストレスを与え、職場環境を悪化させる要因となります。
Q2. 高圧的な上司はなぜ生まれるのですか?
A. 高圧的な上司が生まれる背景には、自分の考えが正しいと思い込んでいる、過去に自分も高圧的な上司のもとで働いた経験がある、自分に自信がなく弱さを隠すために強く見せている、部下を成長させるためにあえて厳しい言葉を使っている、といった理由があります。上司の心情を理解することが、適切な対応につながります。
Q3. 職場でハラスメントを受けている人の割合はどれくらいですか?
A. 2024年度にドクタートラストが実施したストレスチェックでは、職場でハラスメントを受けていると回答した人の割合が5.5%でした。また、厚生労働省の調査では、過去3年間にパワーハラスメントに関する相談があった企業はおよそ6割に上ります。
Q4. パワーハラスメントの行為者として最も多いのは誰ですか?
A. 厚生労働省の職場のハラスメントに関する実態調査報告書によると、パワーハラスメントの行為者として最も多いのは「上司(役員以外)」で65.7%、次いで「会社の幹部(役員)」が24.7%でした。上司からのパワハラが最も多い状況です。
Q5. 理想的な上司を増やすために企業ができることは何ですか?
A. 理想的な上司を増やすためには、理想の上司像について社内で共通認識を持つこと、経営層が積極的に情報発信すること、管理職向け研修(アンガーマネジメント、ハラスメント、傾聴スキル)を定期的に実施すること、部下からアンケート形式で意見を徴収することなどが有効です。継続的な取り組みが重要です。
Q6. 高圧的な上司と上手く働くためのポイントは?
A. 高圧的な上司と上手く働くためには、まず上司の心情を理解することが重要です。上司が高圧的な態度をとる背景を把握し、冷静に対応することで、関係性を改善できる可能性があります。また、自分の意見を適切に伝える、信頼関係を築く、必要に応じて人事や産業保健スタッフに相談することも大切です。
Q7. 高圧的な上司の態度は組織にどのような影響を与えますか?
A. 高圧的な上司がいると、社員のモチベーションや生産性の低下につながります。また、離職率が上がり、職場の雰囲気が悪化します。組織を成長させるためには、上司のあり方が極めて重要であり、信頼される組織文化を築くことが必要です。
Q8. 企業が継続的に理想的な上司を育成するにはどうすればよいですか?
A. 一度の対策で終わらせず、継続的に改善し、新たな施策を導入することが大切です。定期的な研修の実施、上司自身が自分のあり方を考える機会の提供、部下からのフィードバックの仕組み化など、長期的な視点で取り組むことで、信頼される組織文化をつくることができます。