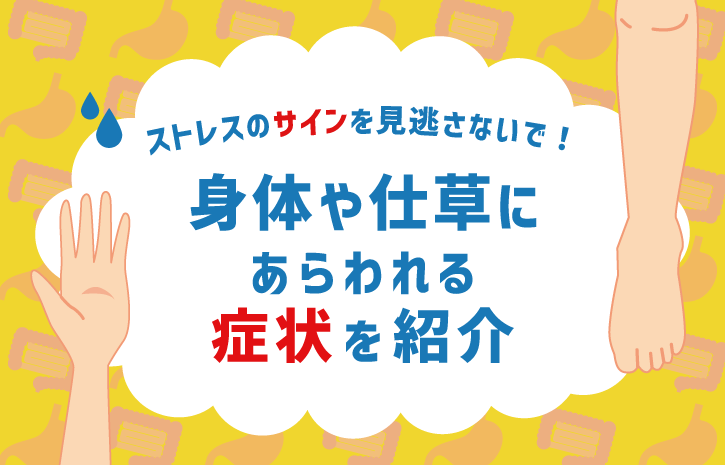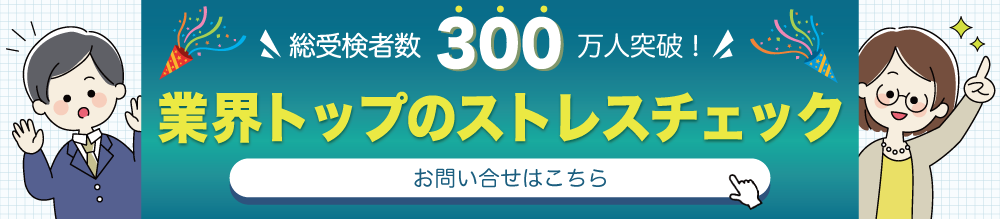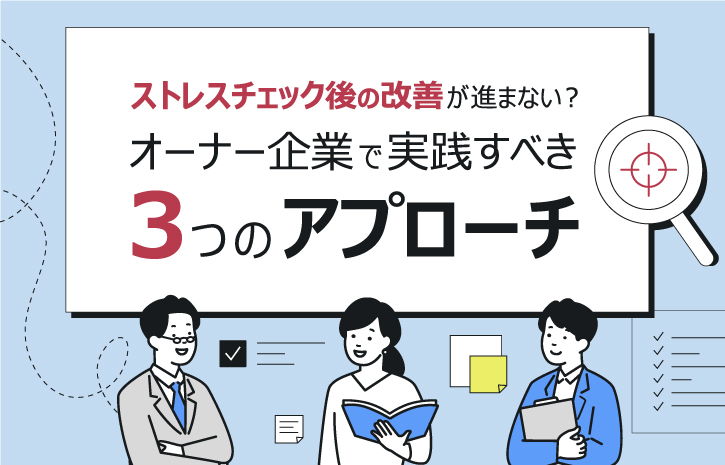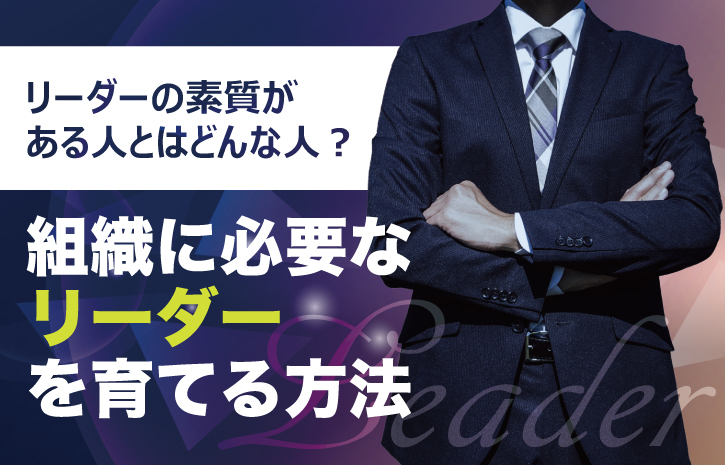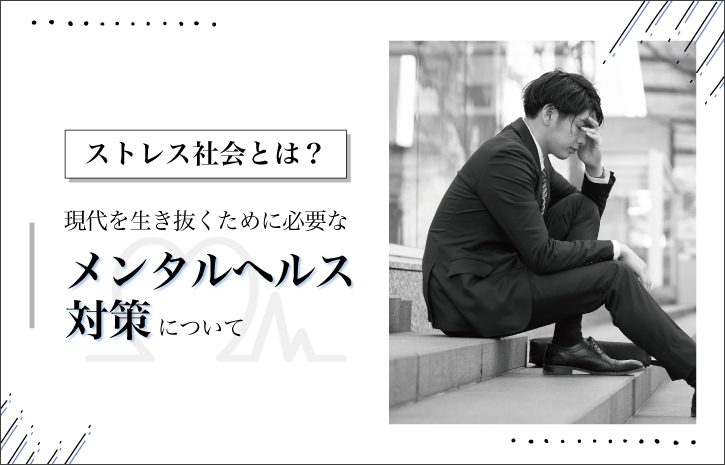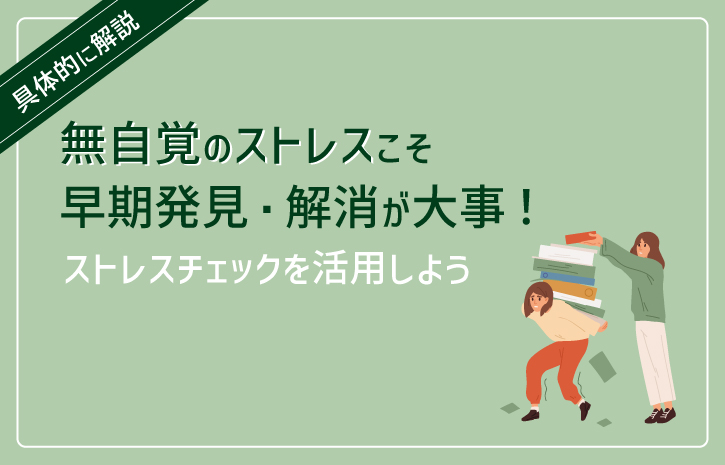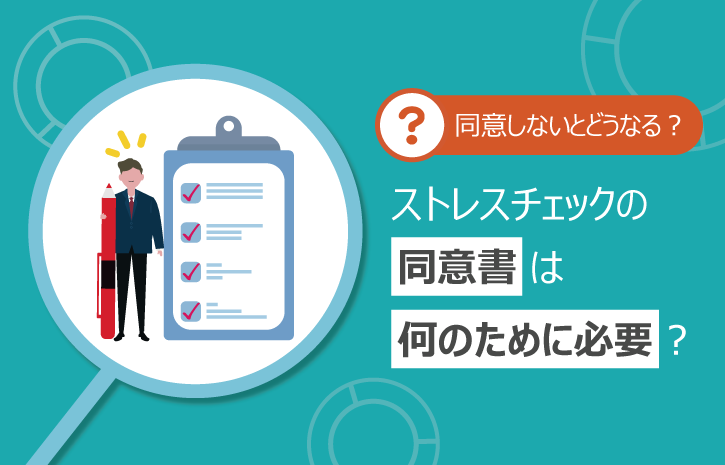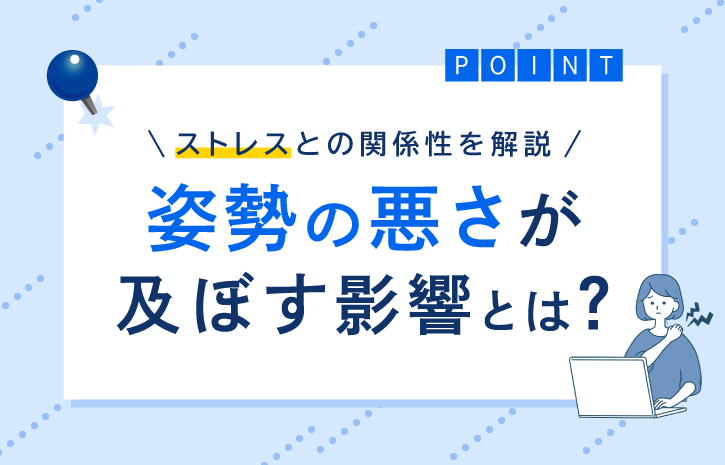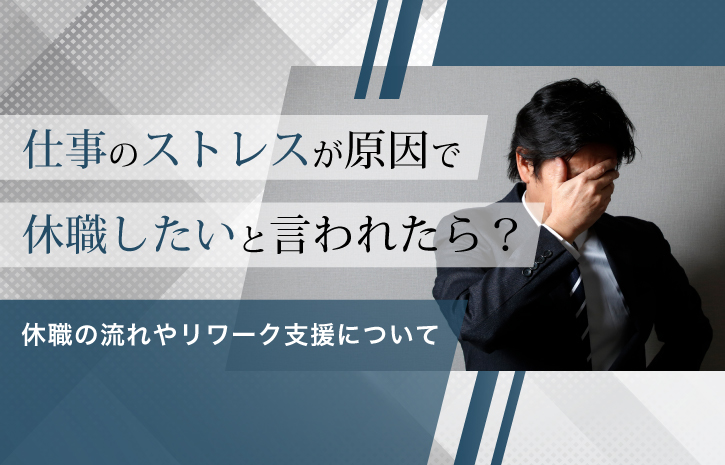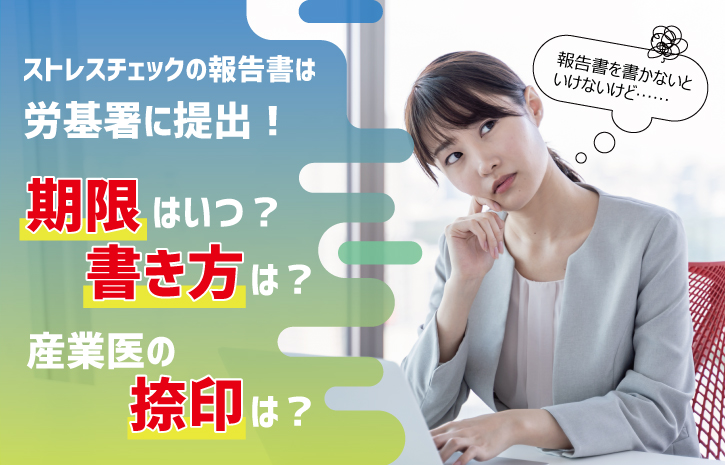みなさんの身近な言葉であるストレス。
具体的にどんな意味かというと、外部からの刺激(ストレッサー)を受けたときに生じる緊張状態のことです。
外部からの刺激とは、天候や騒音など環境によるものや、不安や悩みなどの心理的なもの、人間関係がうまくいかないといった社会的なものがあります。
また、就職や転職、結婚、出産といった、一見喜ばしい出来事も実はストレスの要因になり得ます。
では、このストレスをうまくコントロールできないと、心や体、行動(仕草)にどのような影響があるのでしょうか。
この記事では、人事担当者や管理職が知っておくべきストレスのサインや、その対応方法をご紹介します。
従業員にあらわれるストレスのサイン
ストレスを受けた場合、身体や行動にどんなサインが現れるのでしょうか。
行動(仕草)、身体、発言で把握できるストレスのサインを確認しましょう。
ストレスのサインが見られた場合は対応策の検討が必要です。
行動(仕草)にあらわれるサイン
まず、行動(仕草)に表れるサインは、以下があります。
普段から遅刻をしない社員が遅刻をしたり休みがちになったり、ミスをしない社員のミスが多くなったり……。
普段の様子と比較して著しく行動に変化はないでしょうか。
細かな仕草の変化に気づくためにも、普段の社員や部下の様子を把握しておくことが大切です。
身体の症状にあらわれるサイン
身体の行動のサインとしては、以下があります。
・睡眠障害(不眠など)
・食欲不振や過食
・下痢や便秘
・肩こりや頭痛、腰痛や腹痛などの痛み
・めまいや耳鳴り など
・意欲や集中力の減退
・不安や緊張感が高まる
・落ち込みや憂鬱(ゆううつ)
・涙がでる など
こういったストレスの症状が見られないかを、普段の業務や面談等で確認しましょう。
発言にあらわれるサイン
また、発言に表れるサインとしては以下があります。
・怒りっぽくなる
・口数が減る
・「消えたい」「辞めたい」「何をするのも疲れた」と言う など
普段は温厚なはずの社員が怒りっぽくなったり、口数が減って塞ぎがちになったりしていませんか。
行動や身体のサイン以外でも、業務内や雑談などでの発言の様子からストレスのサインがないかを確認しましょう。
企業に求められる対応
では、こうした症状が見られたら、会社としてどのように対処をしていけばよいでしょうか。
上記でご紹介したストレスのサインが2週間以上続く場合や、日常生活に支障が出ている場合、また、セルフケアに取り組んでいても症状が改善しない場合などは、早めに専門家へ相談することがおすすめです。
産業医面談を勧める
まずは、医療機関の受診や産業医面談の利用などを勧めましょう。
また、会社で設置している相談窓口があれば紹介をしましょう。
専門家に現在の心身の状態について確認してもらい、アドバイスをもらうことでストレスや症状が軽くなることもあります。
社員自身や上司だけで「大丈夫」と判断せずに、専門家の力を借りましょう。
休職を勧める
また、医療機関の受診や産業医面談の結果、休職が必要な場合もあるでしょう。
休職となっても慌てないために、そして、社員が安心して休職ができるよう、休職に関する制度の整備や理解の促進を日頃から進めておくことが重要です。
有給休暇の取得を勧める
ストレスのサインが見られた場合やサインが見られる前に、必要に応じて有給休暇の取得を勧めましょう。
ストレスが慢性的につづくことは、心身の疲労やメンタルヘルス不調にもつながります。
そうなる前に休息をとることが重要です。
社員の中には、業務のコントロールが自分自身では難しい場合があったりや、休息を取らずに頑張りすぎてしまう方がいたりします。
そこで、上司やチームメンバー同士が見守り、休暇がとれるようサポートしあうことが必要不可欠です。
ストレスチェックを実施
また、毎年実施されるストレスチェックでは、仕事でのストレスの要因や社員のこころや体の状態が把握できます。
さらに、ストレスを緩和する周囲のサポートがどれくらいあるかを測定できます。
年1回社員のストレスの状態を把握できる機会ですので、ストレスチェックの分析を活用していくことが、社員のメンタルヘルス不調防止につながります。
管理職のストレスに対する知識が必要
管理職がストレスのサインを理解し対応すること、そして、ストレスチェックの結果を活用することは、社員のメンタルヘルス不調を防ぎ、働きやすい職場にしていくために重要です。
ドクタートラストでは、専門職によるラインケアセミナーのほか、ストレスチェックの集団分析をもとにした職場環境改善サービスを提供しています。
社員がいきいきと働くためにどのようなことをするかお悩みの担当者さまは、ぜひお気軽にお問合せください。