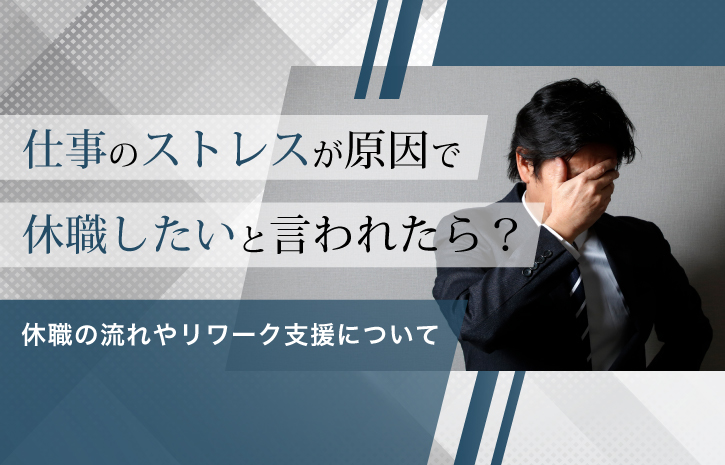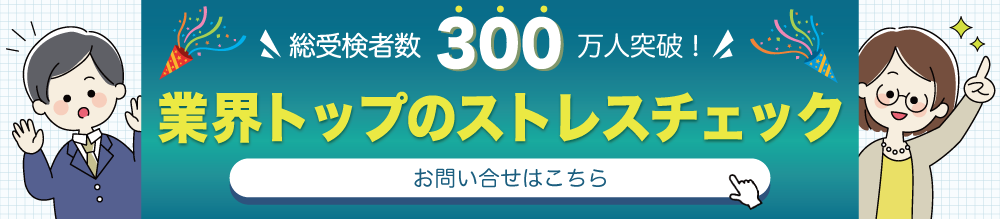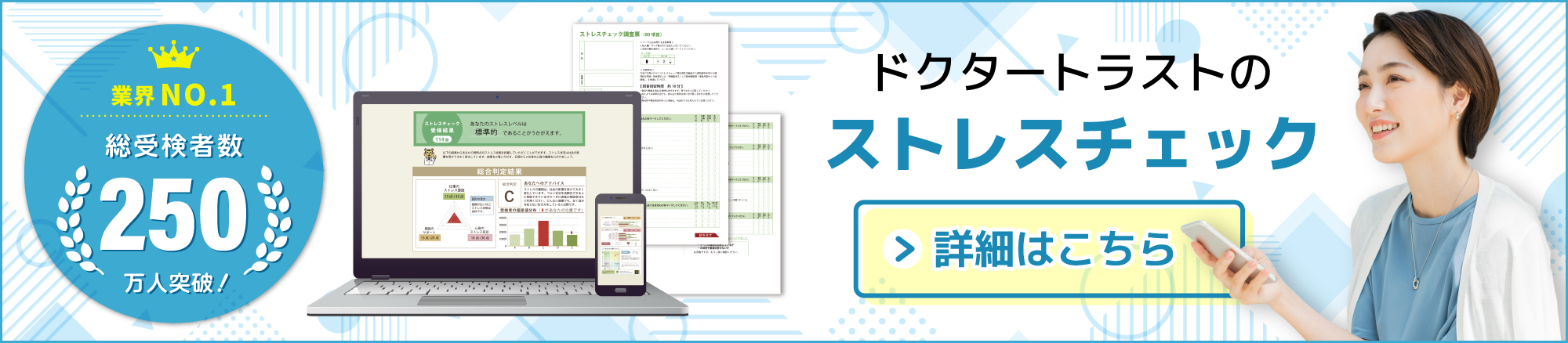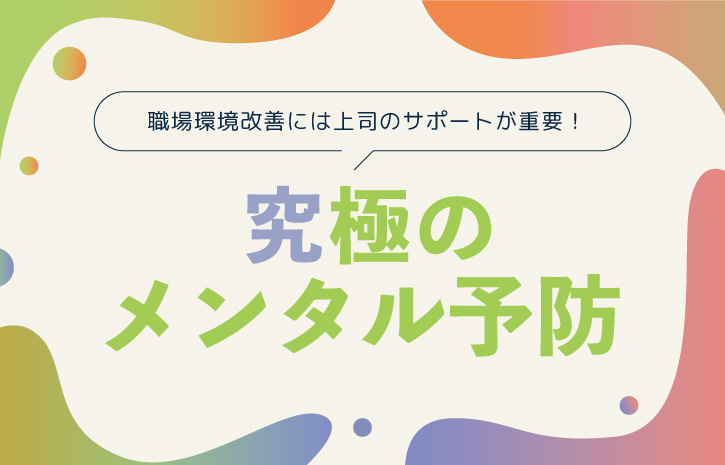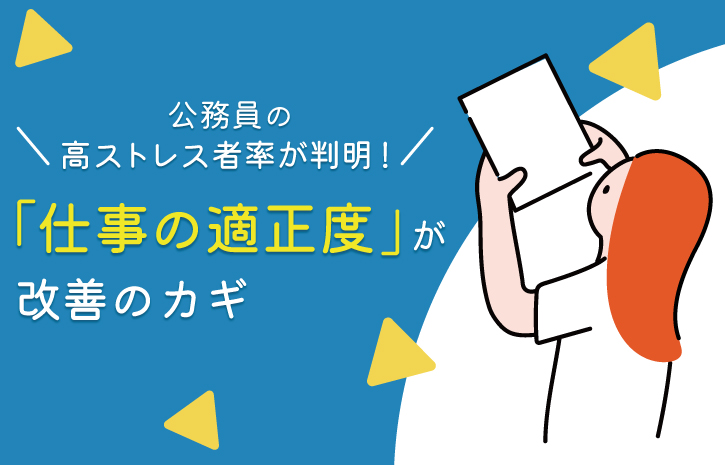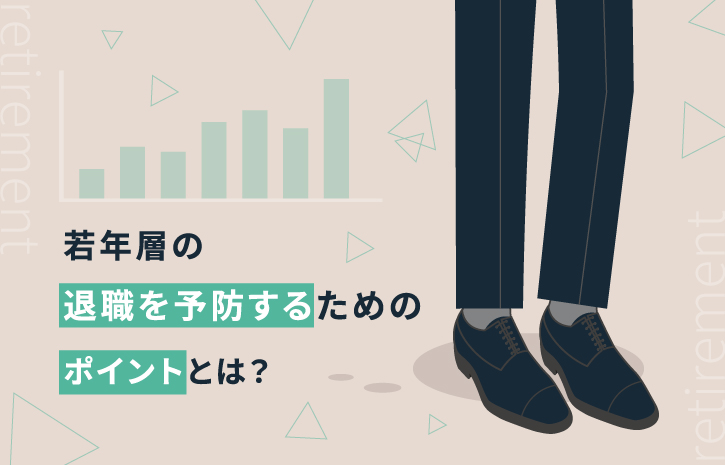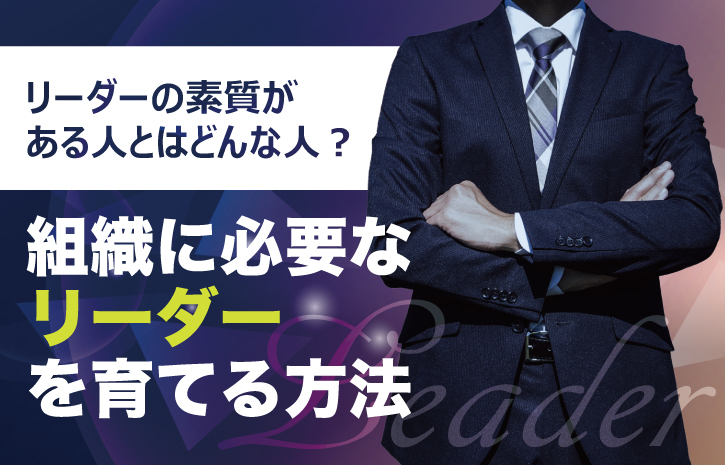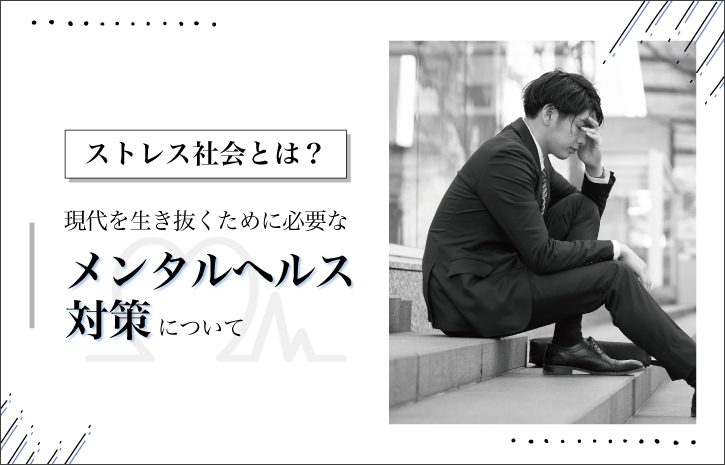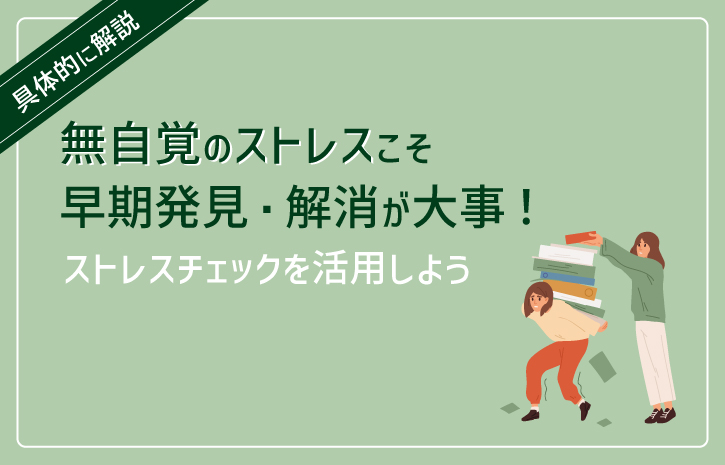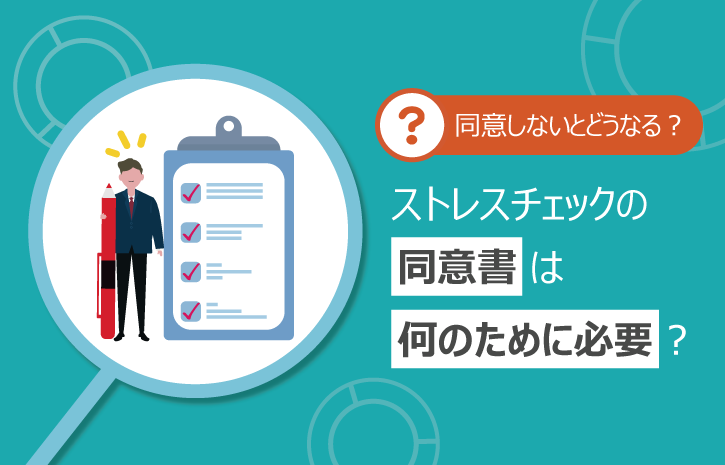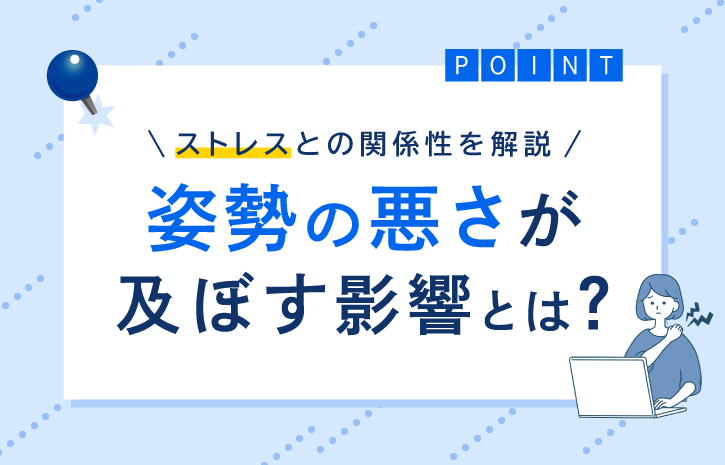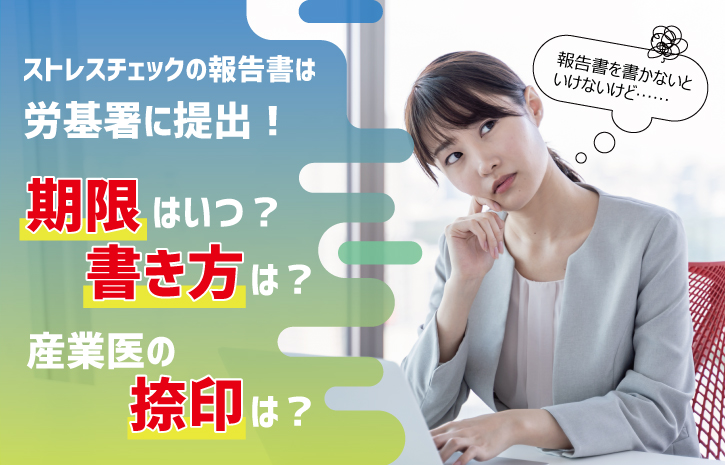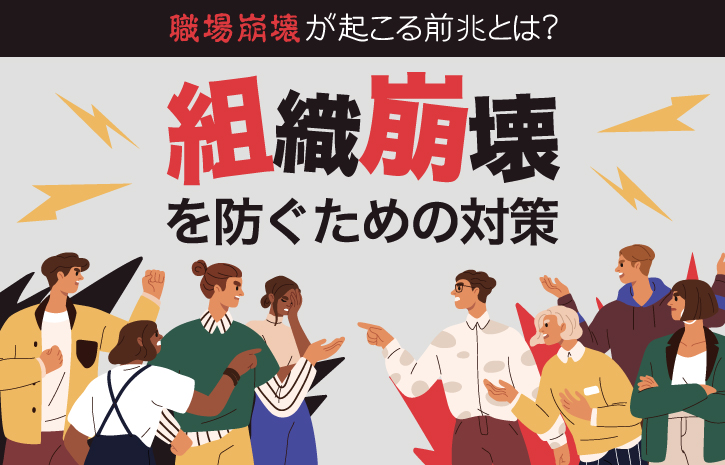従業員が仕事のストレスにより休職を希望した場合、会社としてどのような対応をすれば良いのでしょうか。
主治医からの診断書をもとに産業医と連携し、慎重に判断すべきことが多くあります。
本記事では、休職する際の流れやリワーク支援についてご紹介いたします。
仕事や職場におけるストレスの実態
厚生労働省「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、現在の仕事や職業生活に関して、強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は53.3%と、前年に引き続き過半数を超えています。
また、「仕事の量」「仕事の失敗、責任の発生等」「仕事の質」で特に強い不安やストレスを感じている人が多く、メンタル不調となる要因はさまざまであることがわかります。
メンタルヘルス不調による休職や退職は、本人にとっても辛いばかりか、会社にとっても大きな損失となります。
一次予防としてストレスチェックを実施し、「従業員自身がストレスに気づけているか」「ストレスが発生しにくいような職場環境であるか」などの早期発見が重要です。
仕事のストレスが原因で休職するときの流れ
それでは、従業員が仕事のストレスにより休職を希望した場合の対応を見ていきましょう。
休職期間の決め方
まずは本人の状態を把握するためにも、主治医からの診断書の提出を求めましょう。
診断書を受け取ったら、「どの程度の休職が必要なのか」「どの程度の期間で復職が見込めるか」という点を、産業医と連携し判断します。
主治医の診断は、本人の希望が強く尊重されます。
そのため、勤務時間や職場環境を把握している産業医の判断を踏まえ、会社として休職を認める期間を決定する必要があります。
なお、休職制度は一般的に解雇猶予措置と言われていますので、休職期間について従業員の勤続年数が考慮されるケースもあります。
就業規則を確認し決定していきましょう。
休職中の給与や社会保険負担はどうするか
休職中の従業員に対して、給料を支払う義務はなく、支払うかどうは会社次第です。
就業規則に従い、従業員へ説明を行います。
休職中には無給となるケースが多く、安心して療養に専念できるよう傷病手当金制度についても合わせて案内すると良いでしょう。
ただし、社会保険料については、休職中であっても負担額に変更はなく、休職前と同額の保険料を支払わなくてはいけません。
そのため、社会保険料の支払い方法については、事前に取り決めておく必要があります。
給料の支払いがない場合、休職前のように社会保険料を天引きできなくなるため、従業員から会社へ振り込みをしてもらわなくてはいけません。
会社側が立て替えるケースもありますが、もし従業員の体調が休職期間中に回復せず、退職となってしまった場合には、立て替えた社会保険料を回収できない事態に陥る可能性があります。
休職期間中の過ごし方
休職中は、従業員に業務を忘れて療養に専念してもらえる環境の準備が重要であり、特に休職初期は心身をしっかりと休めてもらうことが優先となります。
会社側からの過度な接触は休職者のプレッシャーになることもあるため、連絡のタイミングや頻度、担当者はあらかじめ決めておきましょう。
産業医や産業保健スタッフと連携したリワーク支援とは
リワーク支援とは、スムーズな職場復帰を目指すリハビリプログラムです。
リワークプログラムを受けてから復職した人のほうが、再休職率が低下するという研究報告もあるため、従業員の体調が安定し、主治医の許可が出たら、リワーク支援を進めていくのが望ましいでしょう。
リワーク支援には以下の3つの種類が存在しており、従業員の意思や状態などから適切なプログラムを選択していきます。
・ 医療機関で行う「医療リワーク」
・ 地域障害者職業センターで行う「職リハリワーク」
・ 企業内で行う「職場リワーク」
リワークプログラムの主な内容としては、仕事に対する集中力を高めるためのオフィスワークやストレスへの対処法を学ぶ認知行動療法、復職後どのような職業人生を送るかを考えるキャリアデザインなどがあります。
費用の負担や対象者、プログラムの内容はそれぞれ異なるので、従業員に合った施設選びが大切です。
まとめ
今回は、休職する際の流れやリワーク支援について紹介しました。
休職・復職の流れは個別性が高く、会社としての対応に悩むケースもあるでしょう。
ドクタートラストでは、会社としての対応に関するアドバイスはもちろん、休職中の従業員をサポートする「アンリケアサービス」や、ストレスチェックを活用した職場環境改善コンサルティングサービス「STELLA」を提供していますので、お気軽にご相談ください。
参考:うつ病からの職場復帰。復職後に安心して働くために事前準備が不可欠|リワーク支援(自立訓練・就労移行)のリワークセンター【Rodina】
ドクタートラストではアンリケアサービスを実施しています。お気軽にお問合せください。
<休職中の社員をサポート>
・アンリケアサービス
よくある質問(Q&A)
Q1. 従業員が休職を希望した場合、まず何をすべきですか?
A. まずは本人の状態を把握するためにも、主治医からの診断書の提出を求めましょう。
診断書を受け取ったら、「どの程度の休職が必要なのか」「どの程度の期間で復職が見込めるか」という点を、産業医と連携し判断します。主治医の診断は本人の希望が強く尊重されるため、勤務時間や職場環境を把握している産業医の判断を踏まえ、会社として休職を認める期間を決定する必要があります。
Q2. 休職期間はどのように決めればよいですか?
A. 主治医からの診断書と産業医の判断を踏まえて、会社として休職期間を決定します。
主治医の診断は本人の希望が強く尊重されますが、勤務時間や職場環境を把握している産業医の判断が重要です。なお、休職制度は一般的に解雇猶予措置と言われていますので、休職期間について従業員の勤続年数が考慮されるケースもあります。就業規則を確認し決定していきましょう。
Q3. 休職中の給与は支払わなければいけませんか?
A. 休職中の従業員に対して、給料を支払う義務はなく、支払うかどうかは会社次第です。
就業規則に従い、従業員へ説明を行います。休職中には無給となるケースが多く、安心して療養に専念できるよう傷病手当金制度についても合わせて案内すると良いでしょう。
Q4. 休職中の社会保険料はどうなりますか?
A. 社会保険料については、休職中であっても負担額に変更はなく、休職前と同額の保険料を支払わなくてはいけません。
そのため、社会保険料の支払い方法については、事前に取り決めておく必要があります。給料の支払いがない場合、休職前のように社会保険料を天引きできなくなるため、従業員から会社へ振り込みをしてもらわなくてはいけません。
会社側が立て替えるケースもありますが、もし従業員の体調が休職期間中に回復せず、退職となってしまった場合には、立て替えた社会保険料を回収できない事態に陥る可能性があります。
Q5. 休職中の従業員とどのように連絡を取ればよいですか?
A. 会社側からの過度な接触は休職者のプレッシャーになることもあるため、連絡のタイミングや頻度、担当者はあらかじめ決めておきましょう。
特に休職初期は心身をしっかりと休めてもらうことが優先となります。休職中は、従業員に業務を忘れて療養に専念してもらえる環境の準備が重要です。
Q6. 現在の職場におけるストレスの実態はどうなっていますか?
A. 厚生労働省「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、現在の仕事や職業生活に関して、強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は53.3%と、前年に引き続き過半数を超えています。
また、「仕事の量」「仕事の失敗、責任の発生等」「仕事の質」で特に強い不安やストレスを感じている人が多く、メンタル不調となる要因はさまざまであることがわかります。
Q7. リワーク支援とは何ですか?
A. リワーク支援とは、スムーズな職場復帰を目指すリハビリプログラムです。
リワークプログラムを受けてから復職した人のほうが、再休職率が低下するという研究報告もあるため、従業員の体調が安定し、主治医の許可が出たら、リワーク支援を進めていくのが望ましいでしょう。
Q8. リワーク支援にはどのような種類がありますか?
A. リワーク支援には以下の3つの種類が存在しており、従業員の意思や状態などから適切なプログラムを選択していきます。
✓ 医療機関で行う「医療リワーク」
✓ 地域障害者職業センターで行う「職リハリワーク」
✓ 企業内で行う「職場リワーク」
費用の負担や対象者、プログラムの内容はそれぞれ異なるので、従業員に合った施設選びが大切です。
Q9. リワークプログラムの主な内容は何ですか?
A. リワークプログラムの主な内容としては、以下のようなものがあります。
✓ 仕事に対する集中力を高めるためのオフィスワーク
✓ ストレスへの対処法を学ぶ認知行動療法
✓ 復職後どのような職業人生を送るかを考えるキャリアデザイン
費用の負担や対象者、プログラムの内容はそれぞれ異なるので、従業員に合った施設選びが大切です。
Q10. メンタルヘルス不調を予防するために何ができますか?
A. メンタルヘルス不調による休職や退職は、本人にとっても辛いばかりか、会社にとっても大きな損失となります。
一次予防としてストレスチェックを実施し、「従業員自身がストレスに気づけているか」「ストレスが発生しにくいような職場環境であるか」などの早期発見が重要です。
ドクタートラストでは、会社としての対応に関するアドバイスはもちろん、休職中の従業員をサポートする「アンリケアサービス」や、ストレスチェックを活用した職場環境改善コンサルティングサービス「STELLA」を提供しています。
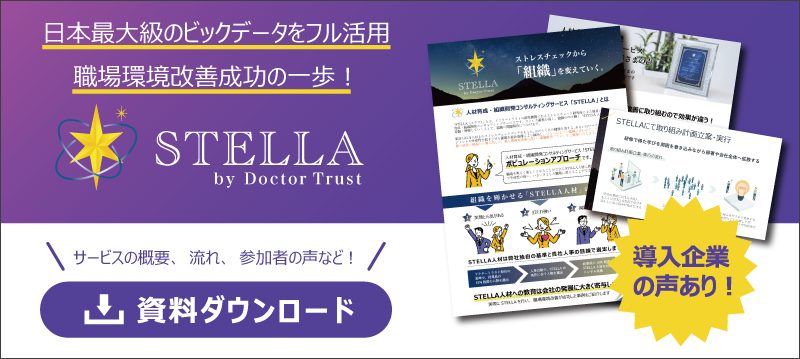
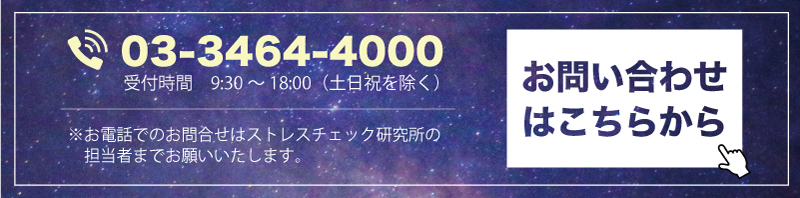
<参考>
厚生労働省「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」