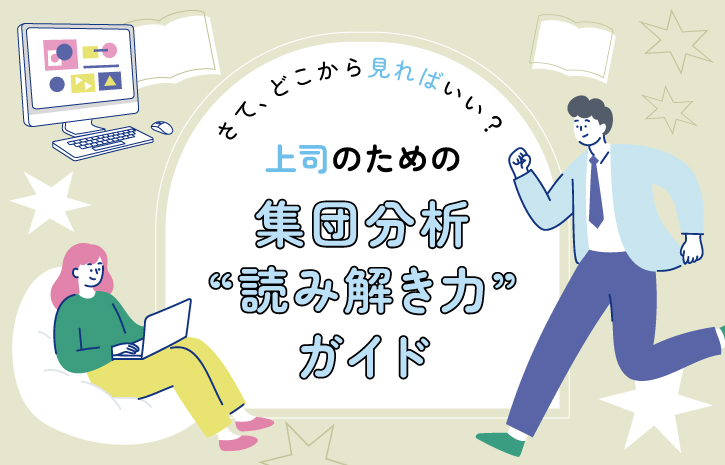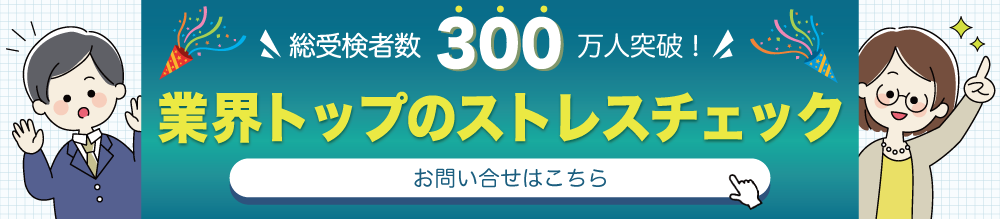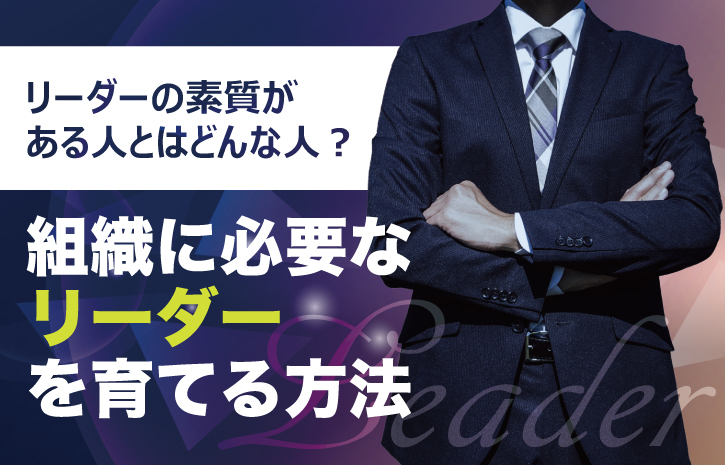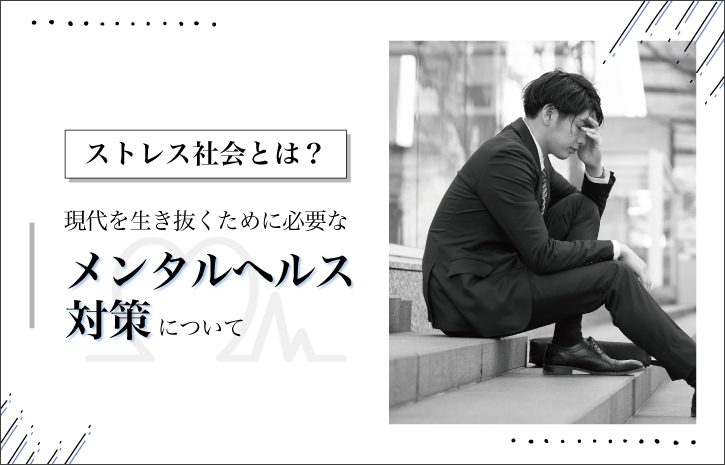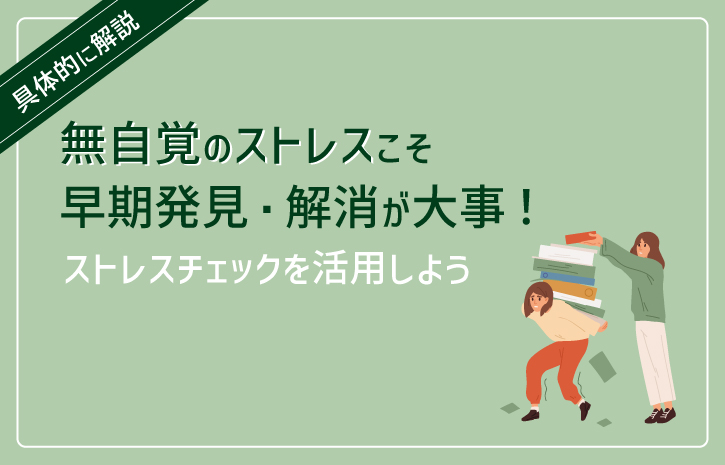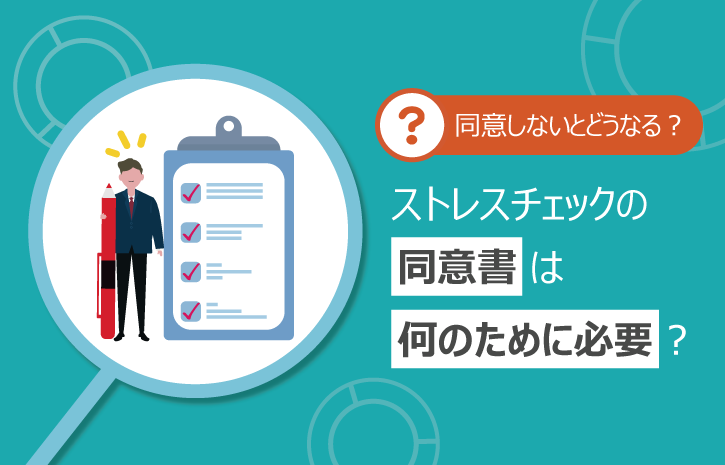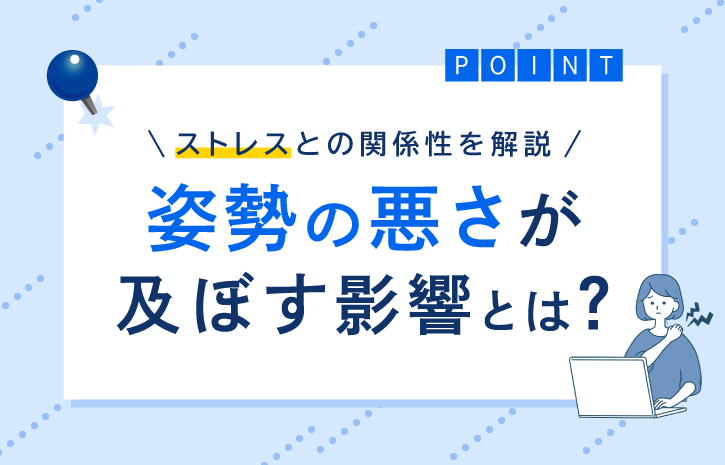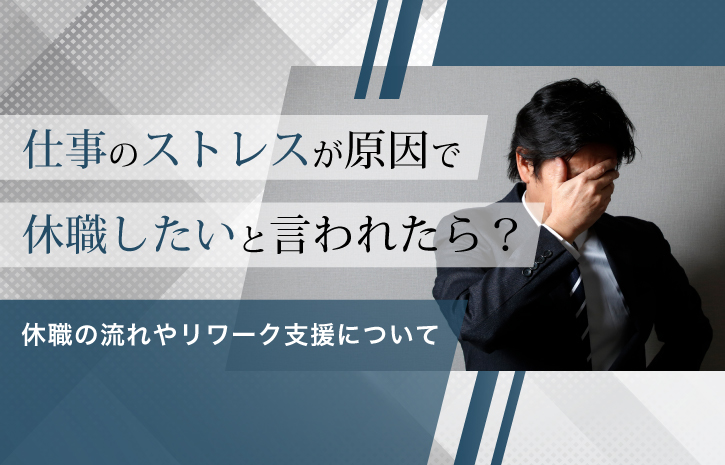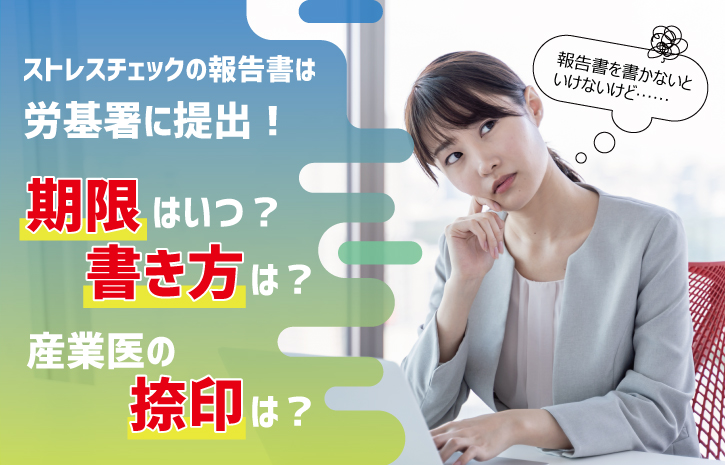職場でストレスチェックが実施されれば、次は「集団分析」を基にフィードバックが行われるのが一般的です。
しかし、グラフや数字が並んだその資料を前に、「結局、どこを見ればいいの?」と戸惑ったことはありませんか?
企業の管理職の方々に対して集団分析結果をもとに1on1を行うと、結果をまるでテストの成績表のように感じるのか、緊張した面持ちで身構えてしまう方も少なくありません。
しかし、集団分析は上司の「評価表」ではなく、あくまで職場の現状を知り、改善の方向を見つけるためのナビゲーションツールにすぎません。
この記事では、初めて集団分析に向き合う上司の方に向けて、「何のために見るのか」「どこをどう読むのか」「どう活かせばいいのか」をわかりやすく解説します。
集団分析ってそもそも何のためのもの?
集団分析とは、ストレスチェックの個人結果を集約し、部署やチームごとの傾向を可視化したものです。
メンバーがどんな負担やストレスを感じているのか、職場の雰囲気やサポート体制がどんな状態にあるのか。いわば職場の健康診断書のような存在です。
確かに現状を数値化し、客観的に見ることができるため「評価表」のように見えるかもしれません。
しかし、ストレスチェックは職場での出来事だけが数値化されているわけではありませんし、結果を受け取る上司に対する内容だけではありません。
集団分析の目的は、問題を「指摘する」ことではなく、「改善の糸口を見つける」ことです。
上司としてこのデータを読み解けば、職場が抱える課題を早期にキャッチし、働きやすい環境づくりやチーム力の向上につなげることができます。
今の結果が仮に悪かったとしても、よい傾向、悪い傾向があるにすぎません。大切なのは現在地から未来に向かって「どう変えていくか」です。
まずはありのままの結果を受け入れましょう。
まずはどこに注目すればいい?
最初に見るべきは、「高ストレス者率」と「健康リスク」の2つです。
高ストレス者率とは、強いストレスを感じている社員の割合を示すもので、全国平均はここ数年15%強です。これよりも高い場合、職場全体に負荷がかかっている可能性があります。
続いて注目したいのが「健康リスク」です。
これは、仕事の量的負担、仕事のコントロール度、上司や同僚からのサポートなど、職場における複数の尺度をもとに算出された、従業員に疾病休業が発生するリスク値を数値化したものです。
リスクが高ければ、「どの要素が影響しているのか」を確認しましょう。
たとえば、「仕事の量が多い」「上司の支援が弱い」など、原因の方向性を見つけていきます。
単に良い悪いで捉えるのではなく、なぜこうなっているのかを考えることが、改善への出発点になります。
また、自部署の結果だけでなく、全社の結果とも比較してみることも大切です。
全社結果が良いのに、自部署の結果が悪ければ注意が必要です。
これって成績表?数値が下がったら人事評価に影響する?
多くの管理職の方々が気にするのが、「この結果は自分の評価に関わるのでは?」という点です。
結論から言えば、集団分析の結果が人事評価に直結することはありません。
数値は「良し悪し」を判断するためではなく、改善のきっかけとして使うものです。
もし一部の数値が低くても、それは改善の方向が見えたにすぎません。
チームの課題が具体的に浮き彫りにし、次のアクションに向けて歩み始めていかなくてはなりません。
そのためには、結果を恐れずにしっかりと見極め、「どうすればメンバーが働きやすくなるか」を前向きに考える姿勢が大切です。
マネジメントに活かすべき尺度
健康リスクなど以外に集団分析の中で、ぜひ注目してもらいたいのが「上司に関する設問」です。
主に以下の設問です。
- ・上司はふさわしい評価をしてくれるか
- ・上司は誠実な態度で対応してくれるか
- ・上司は部下が能力を伸ばせるよう取り計らってくれるか
- ・上司は気軽に話ができるか
- ・困ったときに頼りになるか
- ・個人的な相談をしたらどのくらい聞いてくれるか
これらの設問は、部下が上司のマネジメントをどう感じているかを示す大切な指標です。
偏差値が低い場合は、日常の関わり方やフィードバックの仕方を見直すヒントにしましょう。
逆に高い場合は、信頼関係が築けている証として、今後の強みにできます。
集団分析は“マネジメントの鏡”です。
数値を通じて自分の関わり方を客観的に見直すことで、より良いチーム運営につながるでしょう。
味方につけよう集団分析
集団分析は、単なる統計資料ではありません。
そこには、メンバー一人ひとりの「働きやすさ」や「信頼感」といったリアルな声が詰まっています。
上司がその声を真摯に受け止め、「チームとしてどう変わっていけるか」を話し合うことで、職場の空気は大きく変わります。
結果を一人で抱え込まず、同僚の管理職やメンバーと共有しながら、改善のアイデアを探していきましょう。
上司自身が前向きに結果を受け止める姿勢は、部下に安心感を与え、信頼を育みます。
集団分析を味方につけて、より健康で、より働きやすいチームづくりに向けて一歩踏み出してみましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1. 集団分析とは何ですか?
A. 集団分析とは、ストレスチェックの個人結果を集約し、部署やチームごとの傾向を可視化したものです。
メンバーがどんな負担やストレスを感じているのか、職場の雰囲気やサポート体制がどんな状態にあるのか。いわば職場の健康診断書のような存在です。
Q2. 集団分析の目的は何ですか?
A. 集団分析の目的は、問題を「指摘する」ことではなく、「改善の糸口を見つける」ことです。
上司としてこのデータを読み解けば、職場が抱える課題を早期にキャッチし、働きやすい環境づくりやチーム力の向上につなげることができます。今の結果が仮に悪かったとしても、よい傾向、悪い傾向があるにすぎません。大切なのは現在地から未来に向かって「どう変えていくか」です。
Q3. 集団分析は上司の評価表ですか?
A. いいえ、集団分析は上司の「評価表」ではなく、あくまで職場の現状を知り、改善の方向を見つけるためのナビゲーションツールにすぎません。
確かに現状を数値化し、客観的に見ることができるため「評価表」のように見えるかもしれません。しかし、ストレスチェックは職場での出来事だけが数値化されているわけではありませんし、結果を受け取る上司に対する内容だけではありません。
Q4. 集団分析で最初に見るべきポイントは何ですか?
A. 最初に見るべきは、「高ストレス者率」と「健康リスク」の2つです。
高ストレス者率とは、強いストレスを感じている社員の割合を示すもので、全国平均はここ数年15%強です。これよりも高い場合、職場全体に負荷がかかっている可能性があります。
Q5. 高ストレス者率とは何ですか?
A. 高ストレス者率とは、強いストレスを感じている社員の割合を示すものです。
全国平均はここ数年15%強です。これよりも高い場合、職場全体に負荷がかかっている可能性があります。
Q6. 健康リスクとは何ですか?
A. 健康リスクとは、仕事の量的負担、仕事のコントロール度、上司や同僚からのサポートなど、職場における複数の尺度をもとに算出された、従業員に疾病休業が発生するリスク値を数値化したものです。
リスクが高ければ、「どの要素が影響しているのか」を確認しましょう。たとえば、「仕事の量が多い」「上司の支援が弱い」など、原因の方向性を見つけていきます。
Q7. 自部署の結果だけを見ればいいですか?
A. いいえ、自部署の結果だけでなく、全社の結果とも比較してみることも大切です。
全社結果が良いのに、自部署の結果が悪ければ注意が必要です。単に良い悪いで捉えるのではなく、なぜこうなっているのかを考えることが、改善への出発点になります。
Q8. 集団分析の結果は人事評価に影響しますか?
A. いいえ、集団分析の結果が人事評価に直結することはありません。
数値は「良し悪し」を判断するためではなく、改善のきっかけとして使うものです。もし一部の数値が低くても、それは改善の方向が見えたにすぎません。チームの課題が具体的に浮き彫りにし、次のアクションに向けて歩み始めていかなくてはなりません。
Q9. マネジメントに活かすべき尺度は何ですか?
A. 健康リスクなど以外に集団分析の中で、ぜひ注目してもらいたいのが「上司に関する設問」です。
主に以下の設問です。
✓ 上司はふさわしい評価をしてくれるか
✓ 上司は誠実な態度で対応してくれるか
✓ 上司は部下が能力を伸ばせるよう取り計らってくれるか
✓ 上司は気軽に話ができるか
✓ 困ったときに頼りになるか
✓ 個人的な相談をしたらどのくらい聞いてくれるか
これらの設問は、部下が上司のマネジメントをどう感じているかを示す大切な指標です。
Q10. 上司に関する設問の偏差値が低い場合はどうすればいいですか?
A. 偏差値が低い場合は、日常の関わり方やフィードバックの仕方を見直すヒントにしましょう。
逆に高い場合は、信頼関係が築けている証として、今後の強みにできます。集団分析は”マネジメントの鏡”です。数値を通じて自分の関わり方を客観的に見直すことで、より良いチーム運営につながるでしょう。
Q11. 集団分析の結果をどう活かせばいいですか?
A. 集団分析は、単なる統計資料ではありません。そこには、メンバー一人ひとりの「働きやすさ」や「信頼感」といったリアルな声が詰まっています。
上司がその声を真摯に受け止め、「チームとしてどう変わっていけるか」を話し合うことで、職場の空気は大きく変わります。結果を一人で抱え込まず、同僚の管理職やメンバーと共有しながら、改善のアイデアを探していきましょう。
Q12. 集団分析に向き合うときの心構えは何ですか?
A. 上司自身が前向きに結果を受け止める姿勢は、部下に安心感を与え、信頼を育みます。
結果を恐れずにしっかりと見極め、「どうすればメンバーが働きやすくなるか」を前向きに考える姿勢が大切です。集団分析を味方につけて、より健康で、より働きやすいチームづくりに向けて一歩踏み出してみましょう。