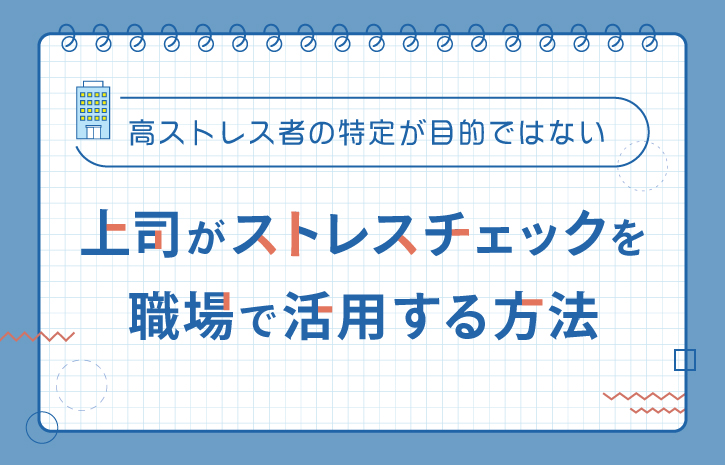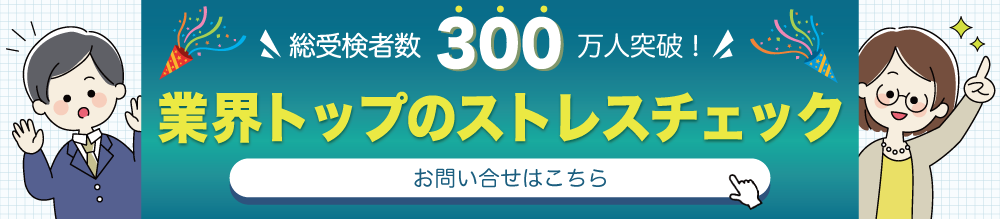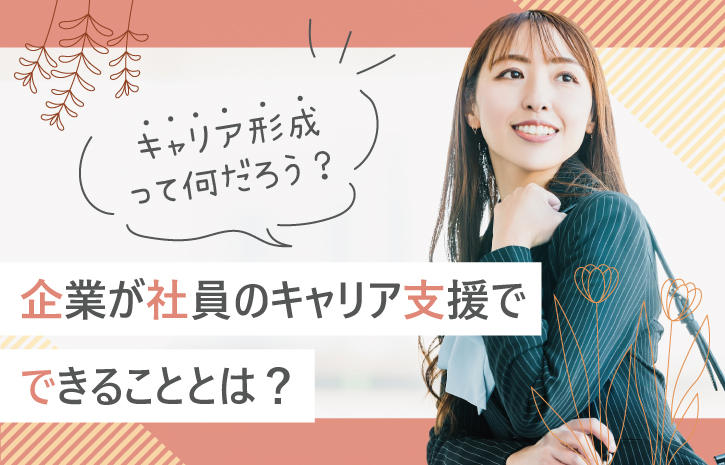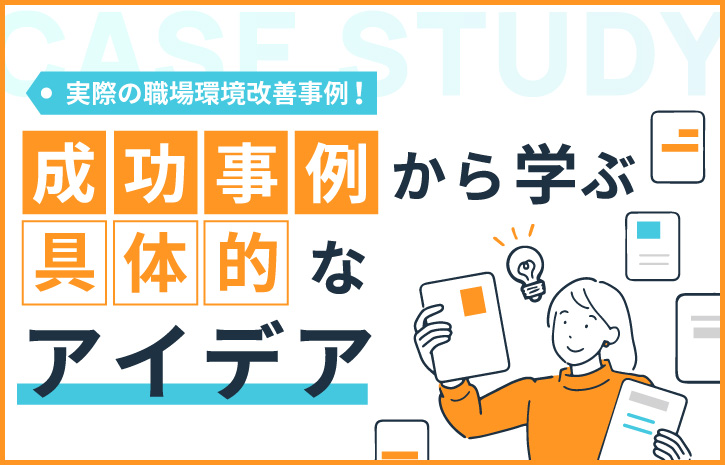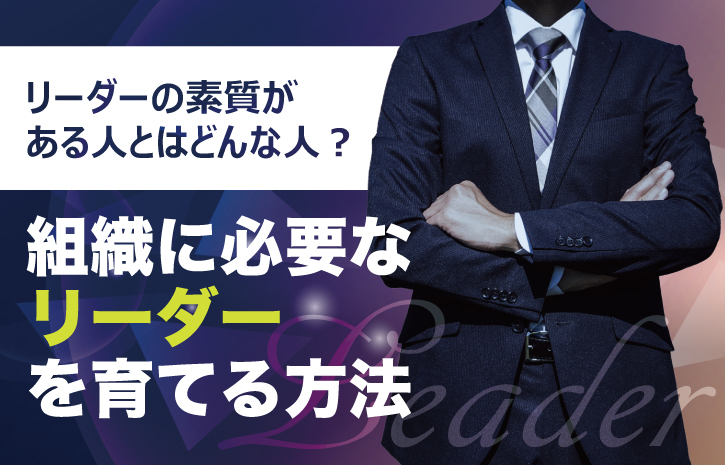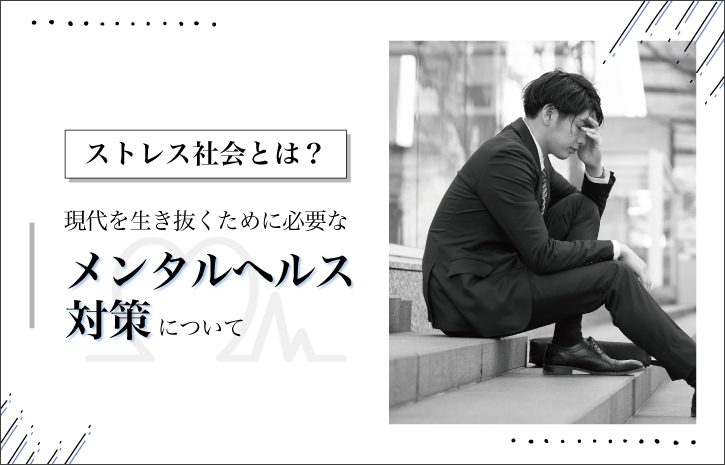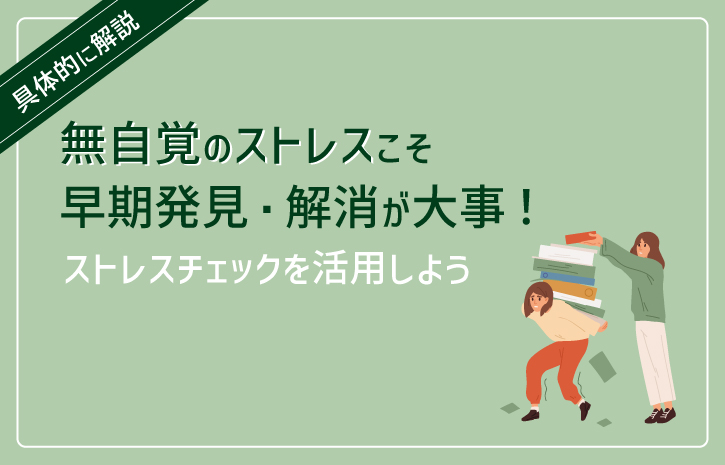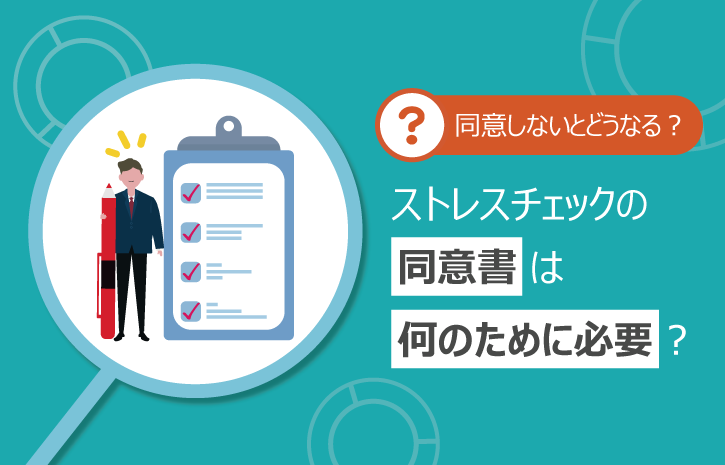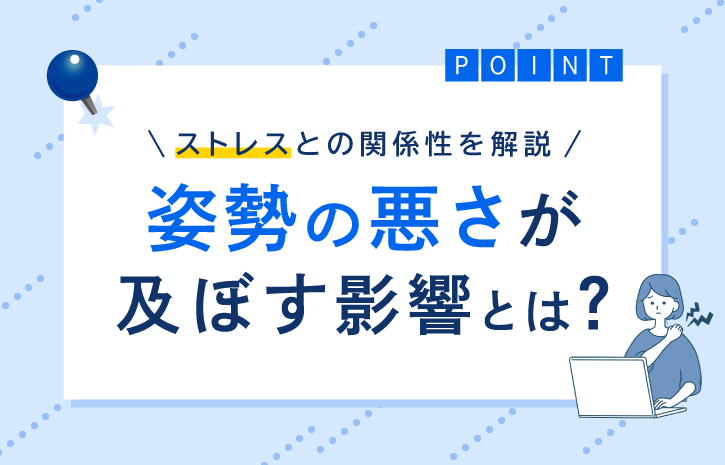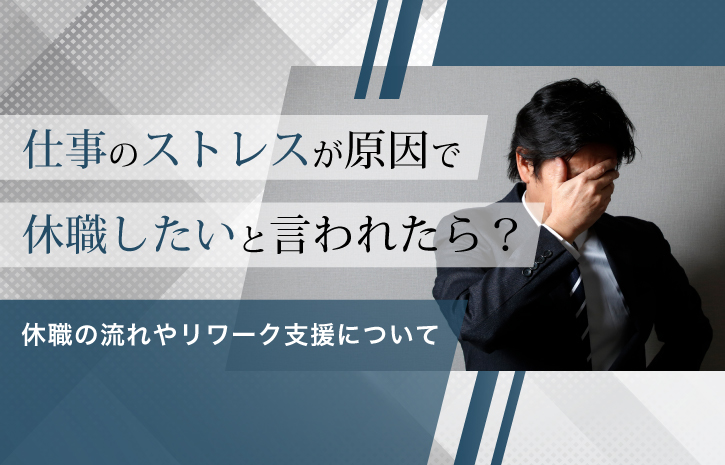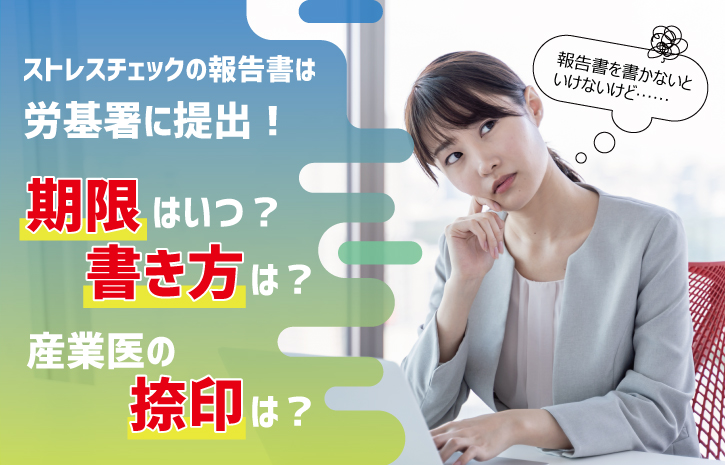働き方の多様化、複雑化に伴い、職場で働く人々のストレスは増加傾向にあります。
厚生労働省の2023年の調査では、「仕事や職業生活に関することで、強い不安、悩み、ストレスと感じる事柄がある」労働者の割合は82.7%でした。
企業におけるメンタルヘルス対策の重要性が高まるなか、ストレスチェック制度は、従業員のストレス状況を把握する有効な手段として推進されています。
ストレスチェック制度は、受検者の不利益取り扱いを防止する目的で、事業者側が個人の結果を知ることは原則できません。しかし、「高ストレス者が誰なのか特定しないと何もできない」という管理職の意見を聞くこともあります。
ストレスチェックにより、「高ストレス者」と判定された従業員に対し、管理職はどこまで関わるべきなのでしょうか。
結論から言えば、管理職は必ずしも「誰が」高ストレス者かどうかを知る必要はありません。
今回はストレスチェックの現状と目的、高ストレス者が多い職場の課題、そして管理職が高ストレス者を特定しなくてよい理由、さらには職場でできる具体的な取り組み例を解説します。
ストレスチェックと「高ストレス者」の定義
ストレスチェックは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査であり、現時点では50人以上の労働者がいる事業場では年1回の実施が義務付けられています。
この検査により、労働者は自身のストレス状況を客観的に知ることができ、職場は集団分析を通じて職場環境の改善に役立てることができます。
ストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判定されるのは以下のいずれかに該当する人です。
・心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目の合計点が高い者
・心身の自覚症状に関する項目の合計点が一定以上で、かつ、仕事のストレス要因と周囲のサポートに関する項目の合計点が著しく高い者
出所元:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度
実施マニュアル」
これらの項目で一定の基準を超えた労働者が高ストレス者とされます。
これは診断ではありませんが、放置するとメンタルヘルス不調に陥るリスクが高まるため、適切な対応が必要です。
高ストレス者が多い職場では、生産性の低下や職場の雰囲気の悪化、離職者の増加、労災リスクの増大などが懸念され、企業への経済的ダメージやイメージの低下だけでなく、安全配慮義務の観点からも、従業員のメンタルヘルスケアに真摯に取り組む必要があります。
管理職は高ストレス者が誰なのかを特定する必要がない4つの理由
メンタルヘルス対策の必要性がある一方で、4つの理由から「管理職は誰が高ストレス者かを知る必要はない」とされています。
1.制度の目的
ストレスチェック制度は、受検者本人が自身の状況を把握しセルフケアに活かすこと、そして組織が集団分析結果から職場環境の改善をすることを目的としています。
もちろん、高ストレス者面談の機会を得て配慮が必要であれば対応は必要です。ただ、同意なく高ストレス者である個人を管理職が特定して個別対応することを本来の目的とはしていません。
集団としての傾向を把握し、組織として活かすことが求められています。
2.個人情報・プライバシーへの配慮
ストレスチェックの結果は、非常にデリケートな個人情報です。
管理職が個人の高ストレス者の情報を把握することは、プライバシーの侵害につながる可能性があります。
同意を得て高ストレス者を特定したところで、それはあくまで一時点での「個人の状態」でしかありません。
「誰が」高ストレス者かを知るよりも、「職場環境の何が要因になるのか」を考え、対応を行う方が効果的です。
3.偏見や差別につながるリスク
管理職が高ストレス者の情報を知ることで、「あの人はストレスに弱い」「問題がある」といった偏見や差別が生じる可能性があります。
高ストレス者という判定は診断ではなく、メンタルヘルス不調者であることを断定するものでもありません。
安易に「良かれと思って」配慮を行うことが、かえって本人の心理的な負担を増大させる要因となりかねません。
4.管理職の役割の限界と負担増
管理職は、人事や労務の専門家ではないため、個々の高ストレス者に対して専門的なカウンセリングや治療を行うことは困難です。
過剰な関わり方が、状況を悪化させる可能性もあります。
また、高ストレス者の割合を気にするあまり、管理職自身がストレスを強く感じ、負担が増加する要因にもなり得ます。
以上の理由から、管理職が個々の高ストレス者情報を把握するよりも、人事担当者や産業保健スタッフとの連携を含め、職場全体の環境改善に取り組むべきと言えます。
高ストレス者が多い職場の取り組み例
高ストレス者が多い職場では、管理職が個々の情報を知るかどうかにかかわらず、部署全体として以下のような取り組みを進めることが重要です。
1.職場環境そのものの改善
ストレスの原因となる職場環境そのものを改善することが最も重要です。集団分析の結果から、ストレス状況が思わしくないのであれば、職場環境の改善が求められます。
業務量の適正化:長時間労働や過度な業務負担の是正、業務の効率化や分担の見直しなど
コミュニケーションの活性化:上司と部下、従業員間のコミュニケーション頻度を増やすため、定期的な面談や意見交換の場を設定など
2. 集団の特徴を捉えた「強みを伸ばす」取り組み
ストレス要因の改善だけでなく、集団分析の回答傾向から集団の特徴を捉え、たとえ同様の状況下でも、やりがいや働きがいを生み出している要因を明らかにして、「強みを伸ばす」取り組みを検討することも有効です。
これらの取り組みは、高ストレス者の発生を未然に防ぎ、職場全体のメンタルヘルスレベル向上を目指すものです。管理職は、これらの取り組みを推進し、職場環境の改善に積極的に関わることが求められます。
まとめ
管理職は、ストレスチェックの結果を組織全体の課題として捉え、高ストレス者が多い職場の環境改善に主体的に取り組む責任があります。
重要なのは、個々の従業員の情報を追求するのではなく、ストレスの原因となる職場環境そのものを改善し、従業員が安心して相談できる体制を構築することです。
管理職は、ラインケアとして、早期に部下の異変に気づき、適切なサポート(専門機関や産業保健スタッフ)につなげる役割を担います。ストレスチェックは、あくまで職場環境改善のためのツールであり、高ストレス者を特定し、管理するためのものではありません。
管理職から個人への働きかけも重要ですが、組織全体で、従業員のメンタルヘルスを尊重し、働きやすい職場づくりを目指すことが、課題解決につながります。ぜひストレスチェックを活用ください。
<参考>
厚生労働省「令和5年『労働安全衛生調査(実態調査)』の概況」
厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
よくある質問
Q1. 管理職は高ストレス者が誰なのかを知る必要がありますか?
いいえ、管理職は必ずしも高ストレス者が誰なのかを知る必要はありません。ストレスチェック制度の目的は、個人のセルフケアと集団分析による職場環境改善です。管理職は個人を特定するのではなく、集団分析結果から職場全体の環境改善に取り組むことが求められます。
Q2. 高ストレス者の情報を管理職が知ることができますか?
原則として、本人の同意なく事業者側が個人の結果を知ることはできません。ストレスチェックの結果は非常にデリケートな個人情報であり、プライバシー保護の観点から厳重に管理されています。高ストレス者本人が面接指導を希望した場合のみ、必要な範囲で情報が共有されます。
Q3. 高ストレス者を特定しなくても職場改善はできますか?
はい、できます。集団分析の結果から、部署や職場全体のストレス傾向を把握し、業務量の適正化やコミュニケーションの活性化など、環境そのものを改善することが効果的です。個人を特定するよりも、「職場環境の何が要因になるのか」を考えて対応する方が根本的な解決につながります。
Q4. 管理職として高ストレス者にどう関わるべきですか?
管理職は、個々の高ストレス者に直接関わるのではなく、日常的なラインケアとして部下の様子を観察し、異変に気づいたら産業保健スタッフや専門機関につなげる役割を担います。専門的なカウンセリングや治療は専門家に任せ、管理職は職場環境の改善に注力すべきです。
Q5. 高ストレス者が多い職場では何から始めればいいですか?
まず集団分析の結果を確認し、ストレスの原因となっている要因を特定します。その上で、業務量の適正化、長時間労働の是正、コミュニケーション機会の増加など、職場環境そのものを改善する取り組みから始めましょう。同時に、従業員が安心して相談できる体制の構築も重要です。
Q6. 高ストレス者判定は診断ですか?メンタルヘルス不調者ということですか?
いいえ、高ストレス者判定は診断ではありません。一時点でのストレス状況を示すものであり、メンタルヘルス不調者であることを断定するものでもありません。放置するとメンタルヘルス不調に陥るリスクが高まる可能性があるため、適切な対応が必要という指標です。
Q7. ストレスチェックで職場の「強み」を見つけることもできますか?
はい、できます。集団分析では、ストレス要因だけでなく、やりがいや働きがいを生み出している要因も明らかにできます。同様の状況下でも良好な結果が出ている部分を「強み」として捉え、それを伸ばす取り組みを検討することで、職場全体のメンタルヘルスレベル向上につながります。