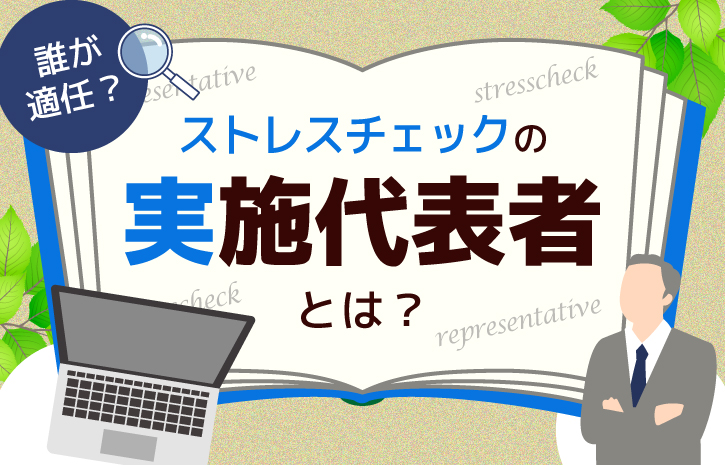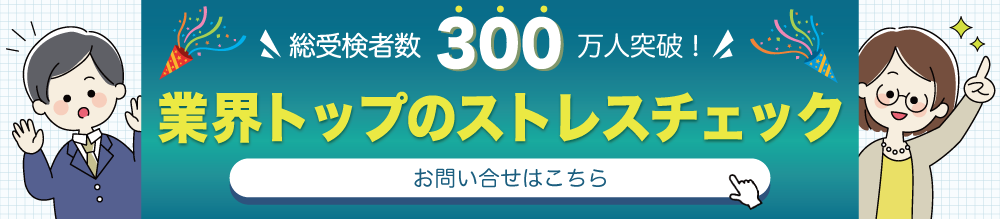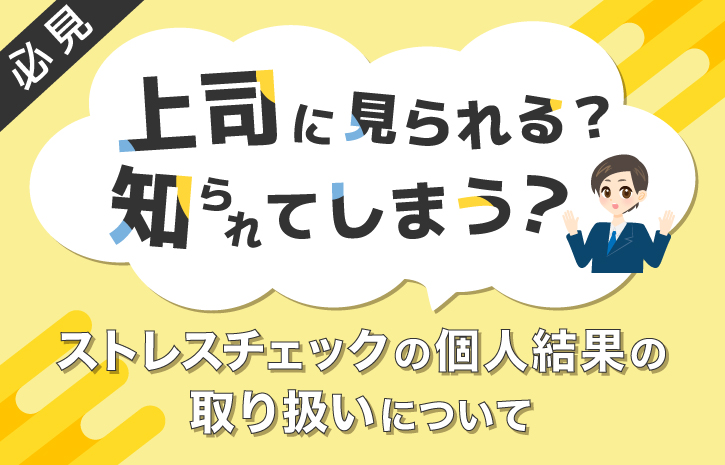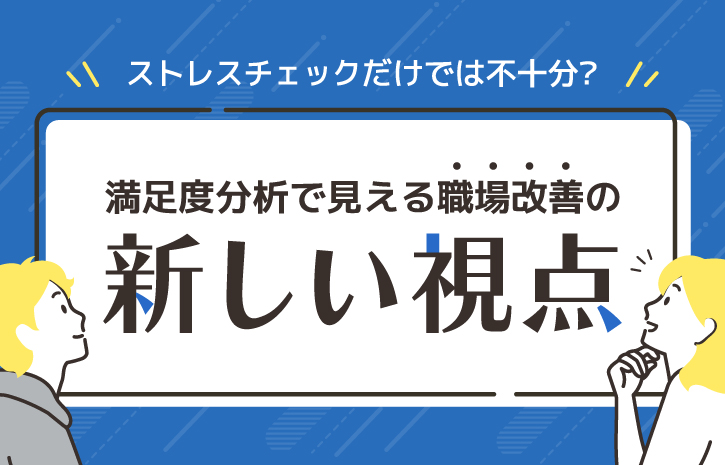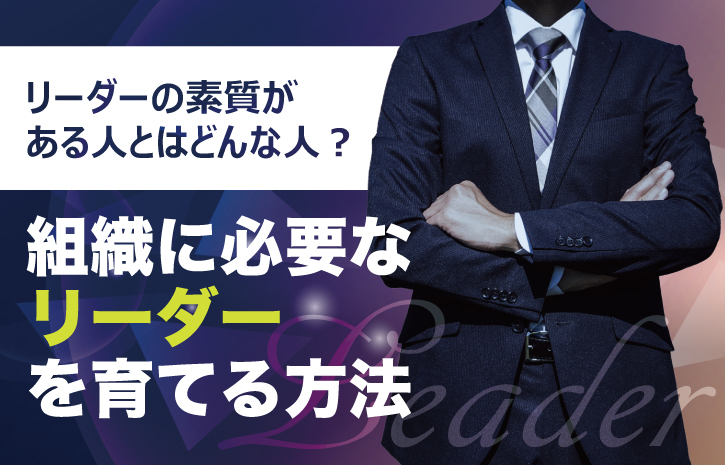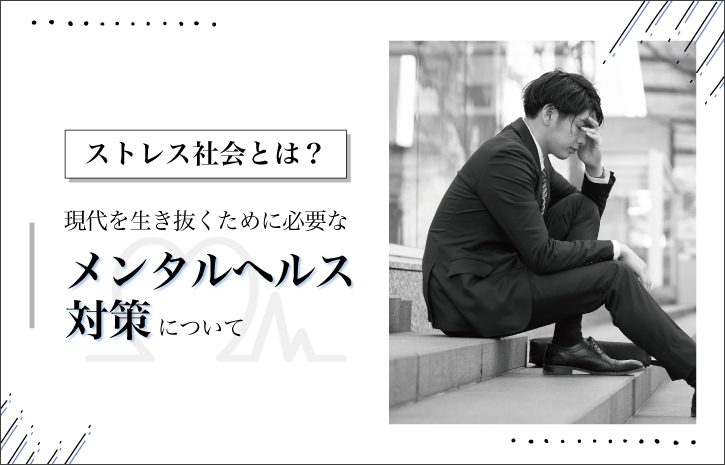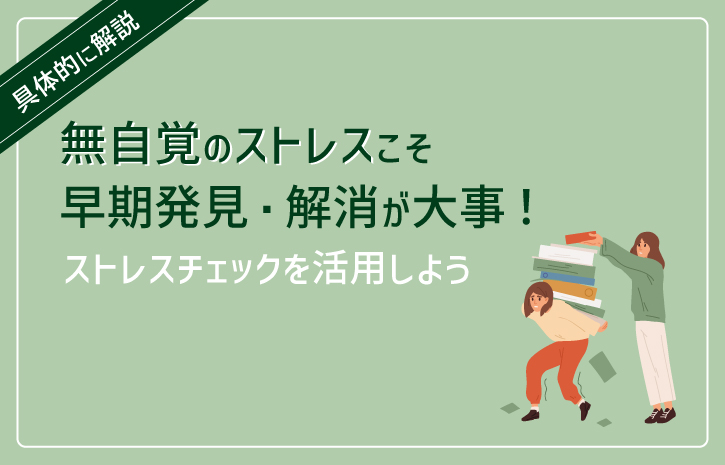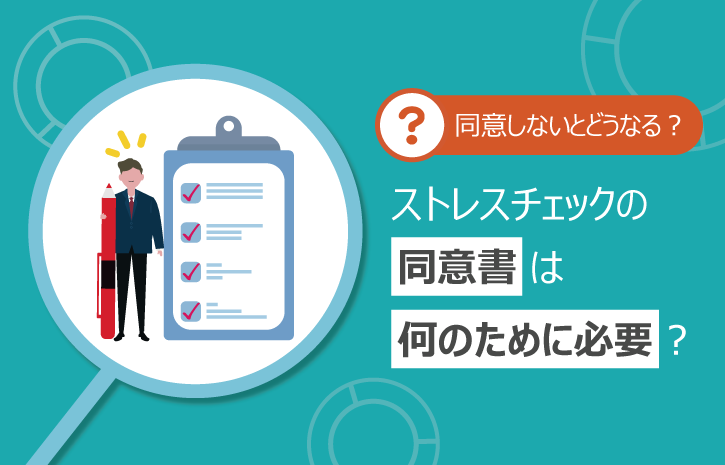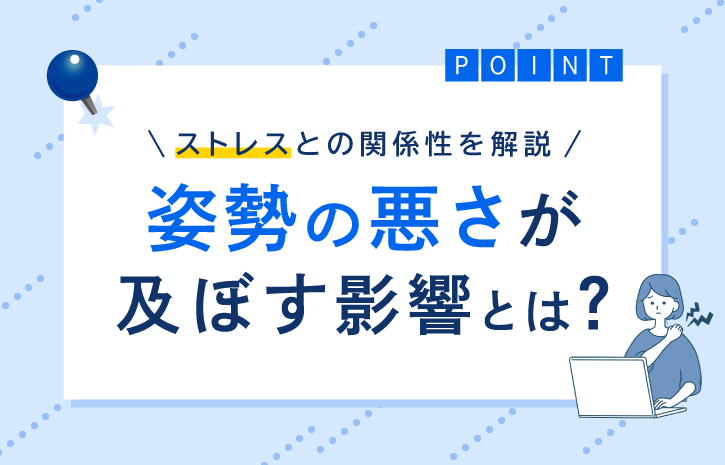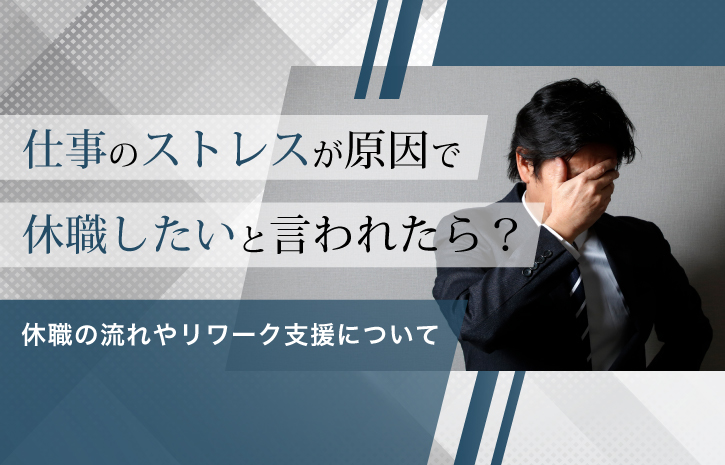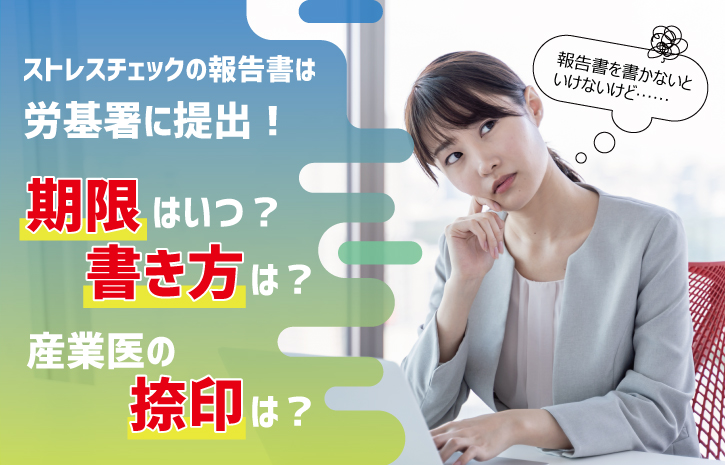2015年12月にスタートしたストレスチェック制度は、労働安全衛生法に基づき、従業員50名以上の事業場に実施が義務づけられています。
その目的は、労働者自身がストレス状況を把握すること、そして高ストレス状態にある人を早期に把握し、医師による面接指導や職場環境改善につなげることにあります。
この制度を実際に運用するうえで中心的な役割を担うのが「実施者」です。複数の実施者がいる場合には「実施代表者」を選任する必要があります。
では、この実施代表者には誰が適任なのでしょうか。
そもそも実施代表者って何?
ストレスチェックにおける「実施代表者」とは、複数の実施者がいる場合に選ばれる代表者です。
実施者には、医師や保健師に加え、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師や精神保健福祉士などが含まれます。もし共同で実施する場合には、その中から「実施代表者」を選任しなくてはいけません。
実施代表者は、ストレスチェックの企画から、調査票の選定、高ストレス者の選定基準の決定、面接指導の要否の確認などの中心的な役割を担い、複数の実施者を代表して事業主と連携します。
実施代表者はだれが適任?
厚生労働省は、ストレスチェック制度に関する指針の中で以下のように述べています。
実施者が複数いる場合は、共同実施者及び実施代表者を明示すること。この場合において、当該事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、当該産業医等を実施代表者とすることが望ましい。
厚生労働省「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置等に関する指針」
つまり、事業場で産業医を選任している場合は、その産業医が「実施代表者」となることが推奨されています。
なぜ産業医が実施代表者として望ましいのか
1. 職場の状況を把握している
産業医は定期的に職場巡視を行い、業務の実態や人間関係、物理的な労働環境を把握しています。
ストレスチェックの結果を解釈する際に、こうした現場情報を踏まえることができるのは大きな強みです。
2. 医学的専門性を持つ
ストレスチェックは心理的な負担を数値化しますが、その結果が心身の健康リスクとどう関わるかを判断するには医学的知識が必要です。
特に高ストレス者への面接指導や医療機関受診の判断は医師である産業医だからこそ対応できる部分があるといえます。
実施代表者が必要となるケースは?
では、実施代表者が必要となるケースにはどんなものがあるでしょうか。
企業の規模が大きく事業所が複数ある場合は複数の実施者が求められるため、実施代表者を選任する必要があります。また、専門性を補完する目的も考えられます。
特殊ですが、もし産業医が人事権を持つ場合は、そもそも実施者になることができないため、複数の実施者を選任し、実施代表者が必要となる場合があります。
労働安全衛生規則に規定されているとおり、人事権を有する者については、その人事権に係る労働者に対するストレスチェックの実施者にはなれません。
そのため、たとえば産業医に部下がいて、その部下に係る人事権を有する場合には、その人事権が及ぶ範囲の部下に対するストレスチェックを実施することはできません。ただし、当該部下以外の労働者(その者が有する人事権とは関係のない労働者)に対するストレスチェックの実施者になることは可能です。
こうした、公平性の確保やリスク分散の視点から実施代表者が必要となるケースもあります。
まとめ
ストレスチェック制度の実効性を高めるためには、単にストレスチェックを実施するだけではなく、結果をどう活かすかが重要です。
厚生労働省が「当該事業場の産業医を実施代表者とすることが望ましい」と明示しているのは、産業医が現場理解、医学的専門性を兼ね備えているからといえます。
事業場で選任している産業医が実施代表者を務めることが難しい場合でも、代わりの実施者が中立性と守秘義務を徹底し、連携を密にすることで、制度の本来の目的である「労働者の心の健康保持増進」を達成できる体制構築につながります。
<参考>
こころの耳「ストレスチェック制度関係 Q&A」
よくある質問(Q&A)
Q1: ストレスチェックの実施代表者とは何ですか?
A: 実施代表者とは、複数の実施者がストレスチェックを共同で実施する場合に選任される代表者です。実施者には医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師や精神保健福祉士などが含まれます。実施代表者は、ストレスチェックの企画、調査票の選定、高ストレス者の選定基準の決定、面接指導の要否の確認などの中心的な役割を担い、複数の実施者を代表して事業主と連携します。
Q2: 実施代表者は誰が適任ですか?
A: 厚生労働省の指針では、「当該事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、当該産業医等を実施代表者とすることが望ましい」とされています。産業医は定期的な職場巡視により職場の状況を把握しており、医学的専門性も持っているため、ストレスチェックの結果を適切に解釈し、高ストレス者への面接指導や職場環境改善につなげることができます。
Q3: 産業医が実施代表者として望ましい理由は何ですか?
A: 産業医が実施代表者として望ましい理由は2つあります。第一に、産業医は定期的に職場巡視を行い、業務の実態や人間関係、物理的な労働環境を把握しているため、ストレスチェックの結果を現場の状況を踏まえて解釈できます。第二に、医学的専門性を持っているため、高ストレス者への面接指導や医療機関受診の判断など、医師だからこそ対応できる部分があります。
Q4: 実施代表者が必要となるのはどんなケースですか?
A: 実施代表者が必要となる主なケースは以下の通りです。①企業の規模が大きく事業所が複数ある場合、複数の実施者が求められるため実施代表者を選任する必要があります。②専門性を補完する目的で複数の実施者を配置する場合。③産業医が人事権を持つ場合、その人事権に係る労働者に対しては実施者になれないため、別の実施者を選任し実施代表者が必要となることがあります。
Q5: 産業医に人事権がある場合、ストレスチェックの実施者になれないのですか?
A: 労働安全衛生規則により、人事権を有する者は、その人事権に係る労働者に対するストレスチェックの実施者にはなれません。たとえば産業医に部下がいて、その部下に係る人事権を有する場合、その人事権が及ぶ範囲の部下に対するストレスチェックを実施することはできません。ただし、当該部下以外の労働者(その者が有する人事権とは関係のない労働者)に対するストレスチェックの実施者になることは可能です。