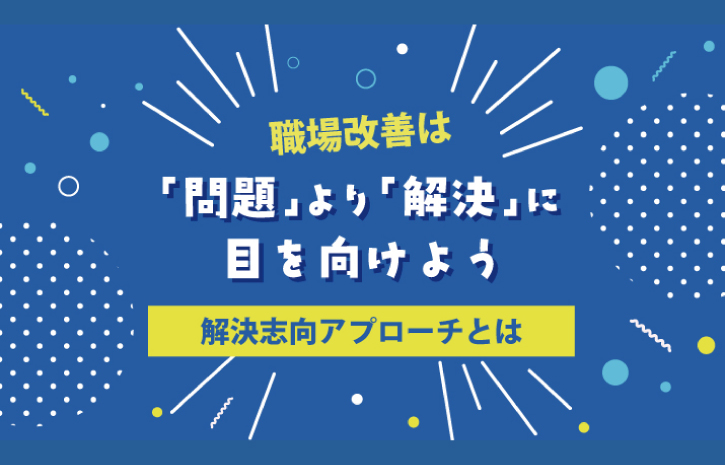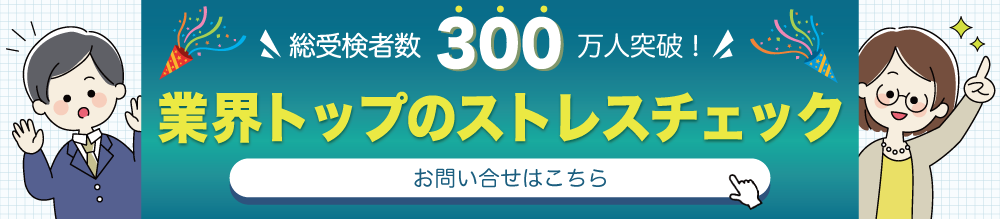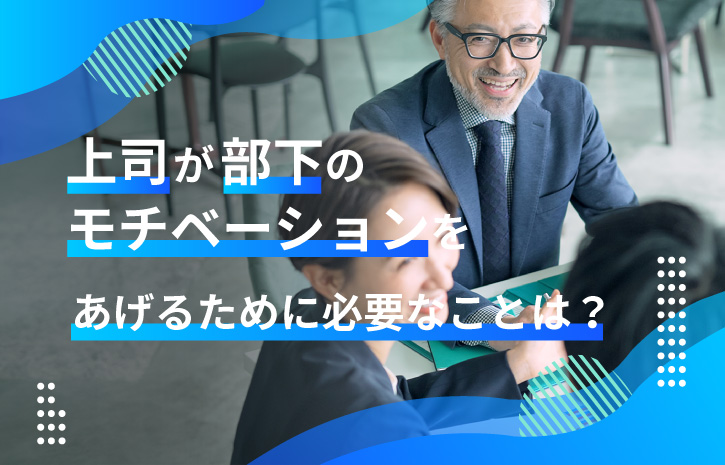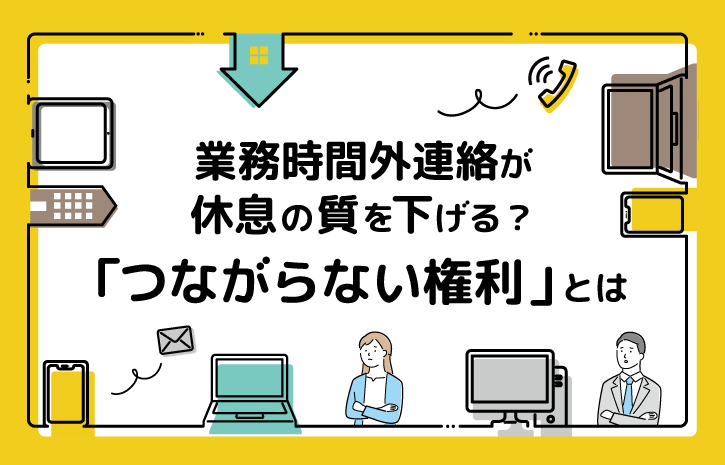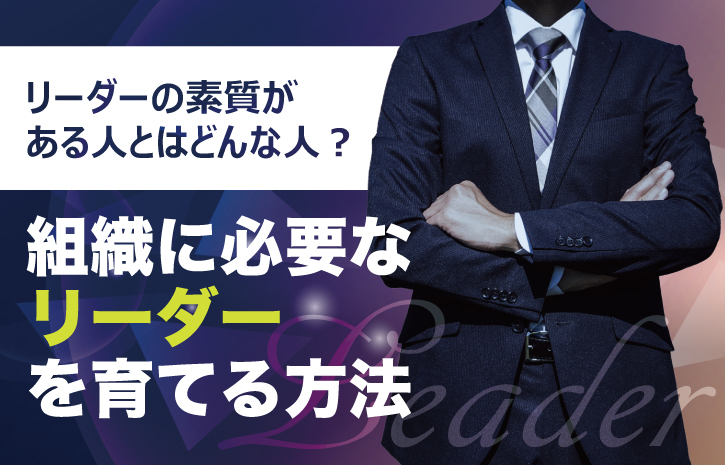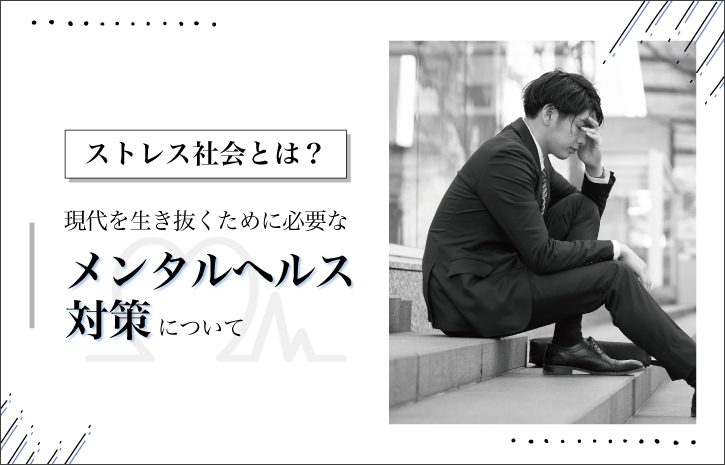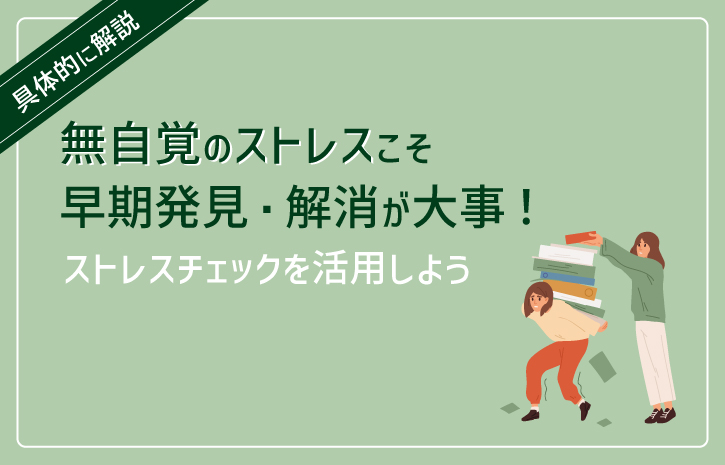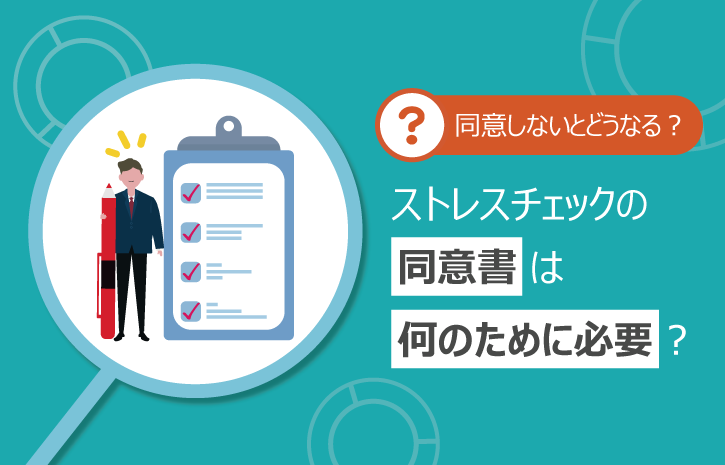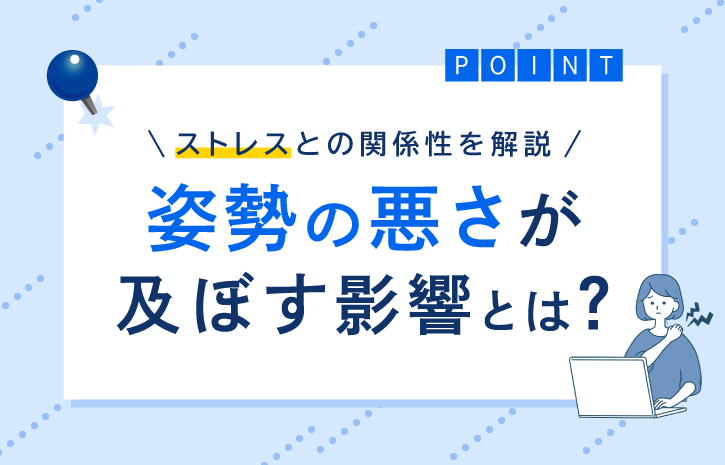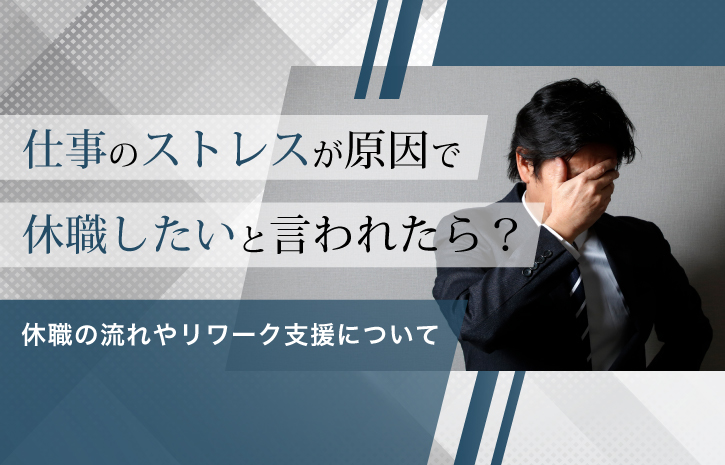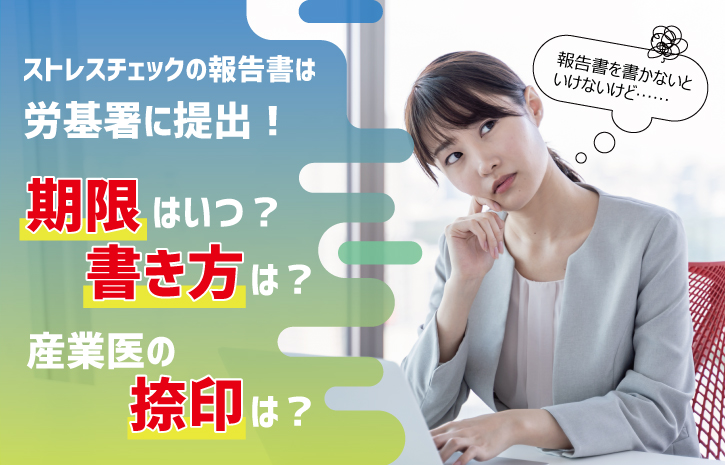職場の雰囲気がなんとなくギスギスしていたり、業務の進行にどこかモヤモヤを感じていたりすると、「どこに問題があるのか?」と考えますよね。
もちろん、こうした課題の把握は組織改善において欠かせないステップです。
しかし、ときには視点を変えてみることで、より前向きで実効性のあるアプローチが見つかるかもしれません。
今回は心理療法の一つであるソリューションフォーカストアプローチ(Solution Focused Approach)、つまり「解決志向アプローチ」という方法をご紹介します。
これは「何が悪いか」ではなく、「何がうまくいっているか」に注目するアプローチです。
問題を深掘りするのではなく、解決に焦点を当てることで、組織にポジティブな変化をもたらす力があるとされています。
まずは、この解決志向アプローチを取り入れるにあたって3つの重要な考えがあるので、一つずつ見ていきましょう。
- 1.うまくいっていることは、無理に変えるな
- 2.うまくいっていることは、もっと増やそう
- 3.うまくいかないことは、やり方を変えてみよう
- まとめ
- よくある質問(Q&A)
- Q1. 解決志向アプローチ(ソリューションフォーカストアプローチ)とは何ですか?
- Q2. 解決志向アプローチの3つの重要な考え方は何ですか?
- Q3. なぜうまくいっていることを変えてはいけないのですか?
- Q4. うまくいっていることを増やすにはどうすればよいですか?
- Q5. 解決志向アプローチは職場改善にどのように役立ちますか?
- Q6. うまくいかないことがあるときはどうすればよいですか?
- Q7. 解決志向アプローチと問題志向アプローチの違いは何ですか?
- Q8. 職場の雰囲気がギスギスしているとき、解決志向アプローチはどう使えますか?
- Q9. 解決志向アプローチで会議の問題を改善するには?
- Q10. 解決志向アプローチを職場に取り入れる第一歩は何ですか?
1.うまくいっていることは、無理に変えるな
私たちは何かを良くしたいとき、新しいやり方や革新的なツールを導入したくなります。
しかし、すでにうまく機能していることまで変えてしまうと、かえって混乱を招いてしまうでしょう。
たとえば、既存の方法でスムーズに業務を進めているのであれば、それを無理に変える必要はありません。
現場の声に耳を傾け、「今のやり方で成果が出ているなら、それを維持する」という選択も大切なのです。
変化を求めること自体は悪いことではありませんが、「変えない勇気」もまた、効果的なマネジメントの一部だといえるでしょう。
2.うまくいっていることは、もっと増やそう
問題が発生したとき、私たちはついダメなところや直すべきことに目が向きがちです。
しかし、解決志向アプローチでは、「今、何がうまくいっているか」を見つけ出し、それを広げていくことに注目します。
たとえば、ある社員が効率的な方法で業務を進めているなら、そのやり方をチーム全体に共有することで生産性が底上げされる可能性があります。
また、チームメンバー同士が自然とサポートし合っている場面を見つけたときに「それ、すごくいいね!」と意識的に評価していけば、その文化が根付くきっかけになるでしょう。
一人ひとりの良いこと・良いところを強化するのは、単に個人の成長を促すだけでなく、職場全体にポジティブな循環をもたらすカギになります。
3.うまくいかないことは、やり方を変えてみよう
同じやり方で何度も失敗を繰り返してしまう、そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか?
解決志向アプローチでは、うまくいかない方法を続けるのではなく、何かまったく新しい別の方法を試すことが大事だと考えます。
たとえば、「会議が長くて生産性が下がっている」と感じているなら、以下のような新しい工夫が考えられます。
このような「今までにない方法」を試すことで、改善の一歩につながるかもしれません。
まとめ
ここまで、解決志向アプローチの考え方を3つ紹介しました。
これらの考え方を取り入れることで、職場に「問題解決」ではなく「成功の再現と拡大」という前向きな空気を作ることができるかもしれません。
問題を深く掘り下げることも時には必要ですが、そればかりでは職場の雰囲気がネガティブになりがちです。
視点を変えて、うまくいっていることに注目する。そんな小さな意識の転換が、働きやすい職場づくりの第一歩になるかもしれません。
よくある質問(Q&A)
Q1. 解決志向アプローチ(ソリューションフォーカストアプローチ)とは何ですか?
A. 解決志向アプローチとは、「何が悪いか」ではなく「何がうまくいっているか」に注目する心理療法の一つです。問題を深掘りするのではなく、解決に焦点を当てることで、組織にポジティブな変化をもたらす力があるとされています。
Q2. 解決志向アプローチの3つの重要な考え方は何ですか?
A. 3つの重要な考え方は以下の通りです。
①うまくいっていることは、無理に変えるな、②うまくいっていることは、もっと増やそう、③うまくいかないことは、やり方を変えてみよう。これらの考え方を取り入れることで、職場に前向きな空気を作ることができます。
Q3. なぜうまくいっていることを変えてはいけないのですか?
A. すでにうまく機能していることまで変えてしまうと、かえって混乱を招いてしまうためです。現場の声に耳を傾け、「今のやり方で成果が出ているなら、それを維持する」という選択も大切です。変化を求めること自体は悪いことではありませんが、「変えない勇気」もまた、効果的なマネジメントの一部といえます。
Q4. うまくいっていることを増やすにはどうすればよいですか?
A. 「今、何がうまくいっているか」を見つけ出し、それを広げていくことに注目します。たとえば、ある社員が効率的な方法で業務を進めているなら、そのやり方をチーム全体に共有することで生産性が底上げされる可能性があります。また、チームメンバー同士が自然とサポートし合っている場面を見つけたときに「それ、すごくいいね!」と意識的に評価していけば、その文化が根付くきっかけになります。
Q5. 解決志向アプローチは職場改善にどのように役立ちますか?
A. 解決志向アプローチを取り入れることで、職場に「問題解決」ではなく「成功の再現と拡大」という前向きな空気を作ることができます。問題を深く掘り下げることも時には必要ですが、そればかりでは職場の雰囲気がネガティブになりがちです。視点を変えて、うまくいっていることに注目する小さな意識の転換が、働きやすい職場づくりの第一歩になります。
Q6. うまくいかないことがあるときはどうすればよいですか?
A. うまくいかない方法を続けるのではなく、何かまったく新しい別の方法を試すことが大事です。たとえば、「会議が長くて生産性が下がっている」と感じているなら、会議の目的を冒頭で明確にする、発言のルールを決めて時間配分を意識する、参加者を厳選するなど、「今までにない方法」を試すことで改善の一歩につながります。
Q7. 解決志向アプローチと問題志向アプローチの違いは何ですか?
A. 問題志向アプローチは「何が悪いか」「どこに問題があるか」に焦点を当てるのに対し、解決志向アプローチは「何がうまくいっているか」「どうすれば解決できるか」に焦点を当てます。問題を深掘りするのではなく、解決に注目することで、よりポジティブで前向きなアプローチが可能になります。
Q8. 職場の雰囲気がギスギスしているとき、解決志向アプローチはどう使えますか?
A. 「どこに問題があるのか」を探すのではなく、「今、何がうまくいっているか」を見つけることから始めます。チームメンバー同士が自然とサポートし合っている場面や、効率的に業務を進めている人の工夫を見つけ、それを意識的に評価し、チーム全体に共有することで、ポジティブな循環をもたらすことができます。
Q9. 解決志向アプローチで会議の問題を改善するには?
A. 「会議が長くて生産性が下がっている」という問題があるなら、以下のような新しい工夫を試すことができます。会議の目的を冒頭で明確にする、発言のルールを決めて時間配分を意識する、参加者を厳選するなど。このような「今までにない方法」を試すことで、改善の一歩につながる可能性があります。
Q10. 解決志向アプローチを職場に取り入れる第一歩は何ですか?
A. 視点を変えて、うまくいっていることに注目することです。問題を深く掘り下げることも時には必要ですが、そればかりでは職場の雰囲気がネガティブになりがちです。一人ひとりの良いこと・良いところを強化することは、単に個人の成長を促すだけでなく、職場全体にポジティブな循環をもたらすカギになります。