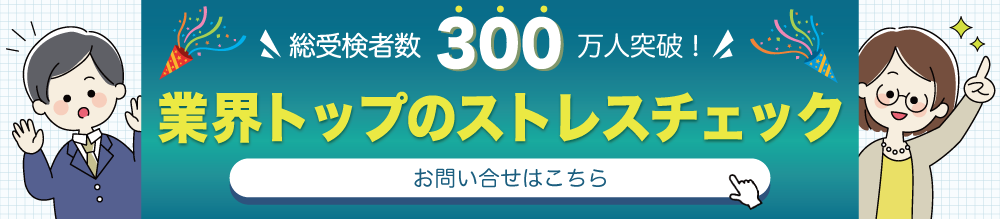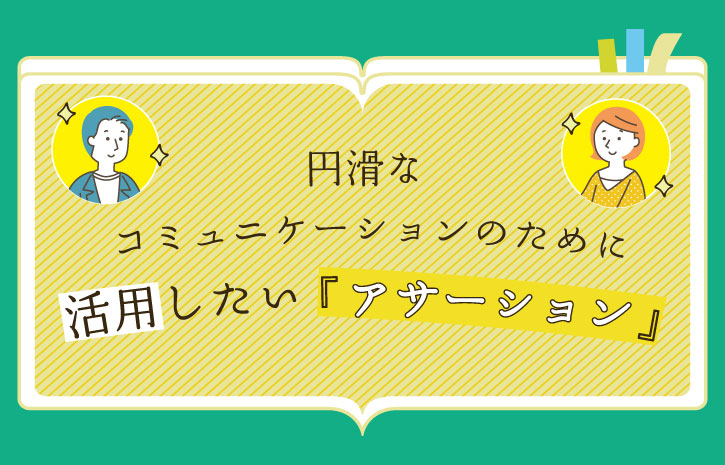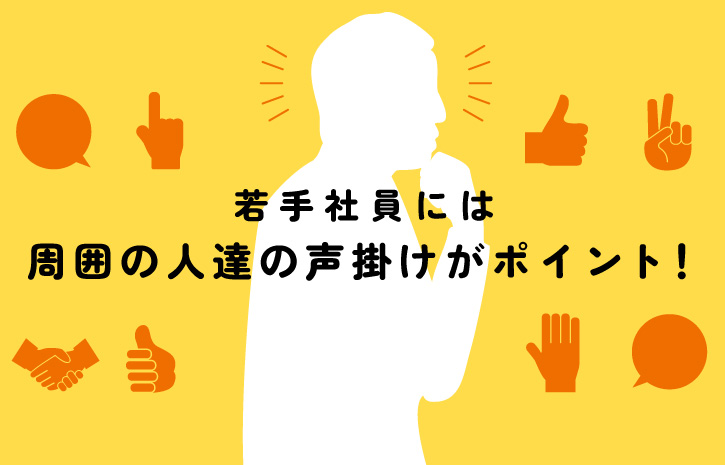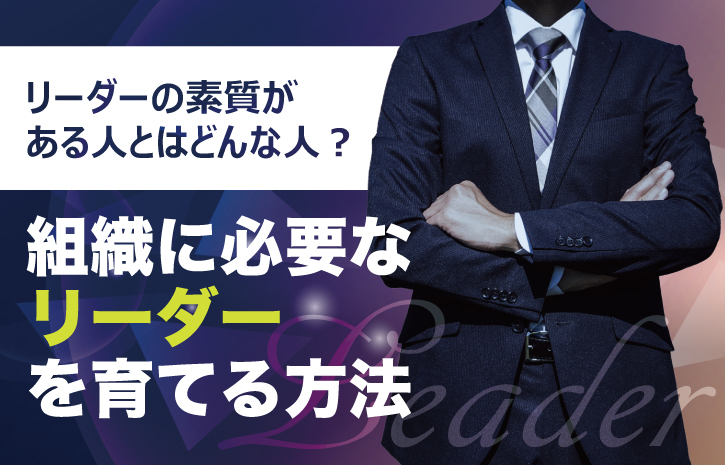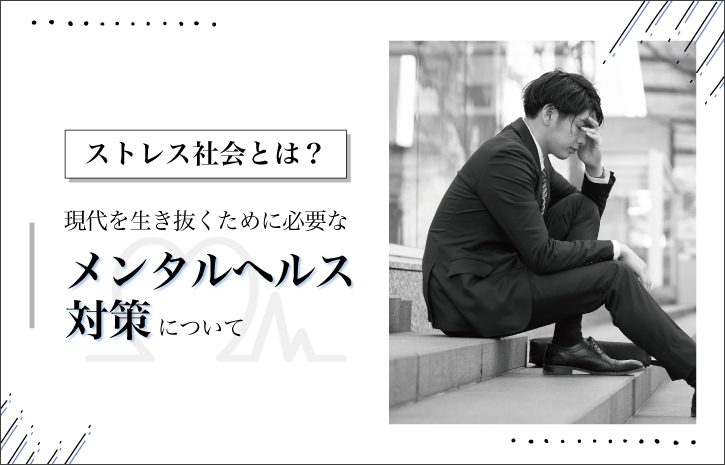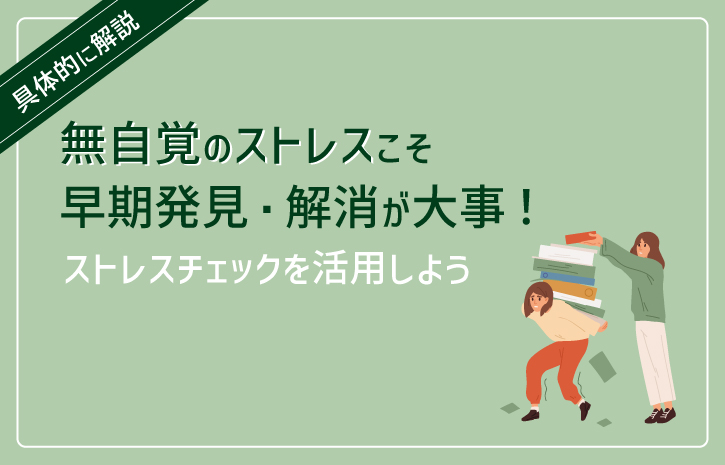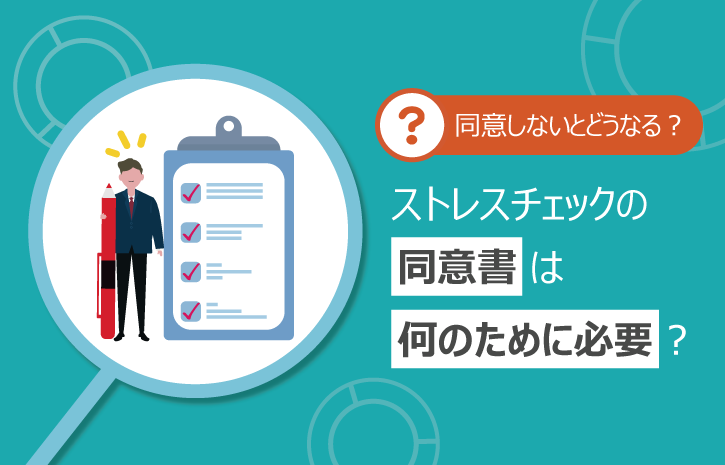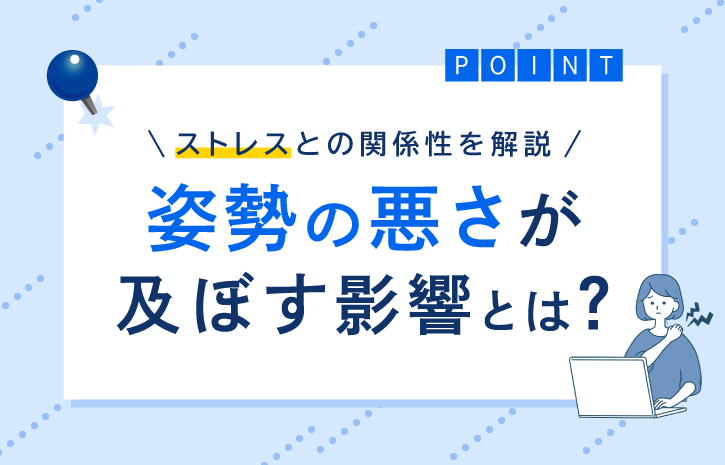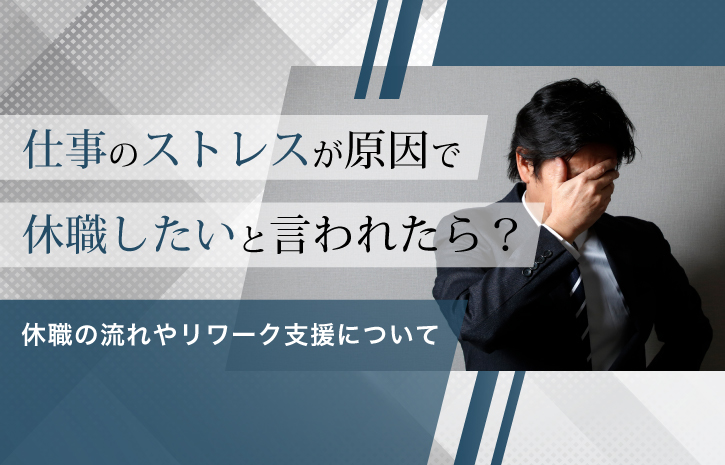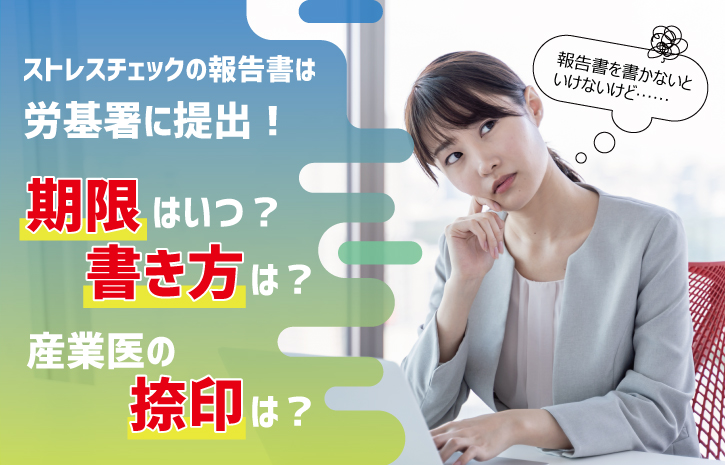ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐだけでなく、組織全体の課題を浮き彫りにし、より健全で生産性の高い組織へと変革する可能性を秘めています。しかし、多くの企業では、ストレスチェックが実施されているものの、その結果を十分に活用できているとは言えません。
本稿では、ストレスチェックの集団分析結果を真に「活かし」、組織強化につなげた具体的な事例を基に、その実践的なアプローチを紹介します。
【事例1】コミュニケーション不全の可視化と風通しの良い組織づくり
課題
ある中堅IT企業では、従業員エンゲージメントの低下と離職率の増加が課題となっていました。
ストレスチェックの集団分析を行った結果、「上司からのサポート不足」や「職場でのコミュニケーション不足」といった項目で顕著な高ストレス者の割合が高いことが判明しました。
分析
詳細な調査(無記名式でのアンケート)を進めた結果、プロジェクトごとの縦割り意識が強く、部署間連携が不足していること、また、管理職がプレイングマネージャーとして業務に追われ、部下との対話時間を十分に確保できていないことが根本的な原因として特定されました。
対策
部署間交流の促進
定期的な部署交流会やシャッフルランチの実施、合同プロジェクトの発足など、従業員間の横のつながりを強化する施策を導入しました。
管理職研修の実施
コミュニケーションスキル向上、部下育成、コーチングに関する管理職研修を実施し、管理職の意識改革とスキルアップを図りました。
1on1ミーティングの義務化と質向上
管理職と部下との定期的な1on1ミーティングを義務化し、その目的や進め方に関するガイドラインを作成・周知しました。
また、1on1ミーティングのスキル向上のためのトレーニングも実施しました。
オープンなコミュニケーションチャネルの導入
社内SNSやチャットツールを活用し、部署内外の従業員が気軽に情報交換や意見交換できる場を設けました。
経過
これらの対策を実施した結果、ストレスチェックの「上司からのサポート」や「職場でのコミュニケーション」に関する項目の改善が見られました。
また、従業員エンゲージメント調査においてもスコアが向上し、離職率も低下傾向に転じました。
従業員からは「以前よりも上司に相談しやすくなった」「他部署との連携がスムーズになった」といった声が聞かれるようになり、組織全体の風通しが明らかに改善しました。
【事例2】業務負荷の偏り是正と効率的な働き方の実現
課題
ある製造業の工場では、特定の部署や担当者に業務負荷が集中しており、恒常的な長時間労働が問題となっていました。
ストレスチェックの集団分析では、「仕事の量的負担」や「仕事のコントロール感の低さ」が高ストレス要因として示されました。
分析
業務プロセスを詳細に分析した結果、業務の標準化が不十分であること、担当者ごとのスキルレベルにばらつきがあること、また、一部の業務が属人化していることが業務負荷の偏りと長時間労働の背景にあると分かりました。
対策
業務の可視化と標準化
各業務のプロセスを洗い出し、標準化マニュアルを作成しました。
これにより、誰でも一定の品質で業務を遂行できる体制を構築しました。
多能工化(マルチタスク化)の推進
従業員のスキルマップを作成し、OJTや研修を通じて多能工化(マルチタスク化)を推進しました。
これにより、業務負荷の調整や人員配置の柔軟性を高めました。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入
定型的な事務作業やデータ入力業務にRPAを導入し、従業員の負担を軽減しました。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、これまで人が行ってきた業務をソフトウェアやAIを使って効率化を図る取り組みです。
タスク管理ツールの導入と活用
プロジェクトやタスクの進捗状況を可視化するタスク管理ツールを導入し、チーム内での情報共有を促進しました。
経過
これらの対策により、ストレスチェックにおける「仕事の量的負担」の項目が大幅に改善されました。また、残業時間も減少し、有給取得率が向上するなど、従業員のワークライフバランスが改善されました。
業務効率化が進んだことで、生産性の向上にもつながり、組織全体のパフォーマンス向上に貢献しました。
従業員からは「以前よりも時間に余裕ができた」「自分のペースで仕事を進められるようになった」といった声が聞かれました。
【事例3】ハラスメント対策と心理的安全性の向上
課題
あるサービス業の企業では、新人が入ってきてもすぐに辞めてしまい、慢性的な人で不足に悩んでいました。ストレスチェックの集団分析では、「職場のハラスメント」に関する項目で高ストレス者の割合が高いことが明らかになりました。
分析
従業員へのヒアリング調査を実施した結果、一部の上司や先輩社員によるパワハラや、顧客からの理不尽な要求に対するサポート体制の不備がハラスメント発生の要因として特定されました。
対策
ハラスメント防止研修の徹底
全従業員を対象に、ハラスメントの種類や影響、相談窓口などを周知する研修を定期的に実施しました。
ハラスメント相談窓口の設置と周知
独立した相談窓口を設置し、相談しやすい環境を整備しました。
相談者のプライバシー保護を徹底し、安心して相談できることを周知しました。
顧客対応マニュアルの作成と研修
顧客からの理不尽な要求への対応方法や、上司や責任者の判断を仰ぐ際(エスカレーション)のルールを明確化したマニュアルを作成し、従業員への研修を実施しました。
管理職への意識啓発
管理職に対し、ハラスメント防止の重要性や、部下への適切な指導方法に関する研修を実施し、ハラスメントのない職場づくりへの意識を高めました。
経過
これらの対策により、ストレスチェックにおける「職場のハラスメント」に関する項目の改善が見られました。
自分がハラスメント行為を行っていると認識のなかった管理職が正しい認識を得たことで、その行動に変化がありました。
また、会社がハラスメントに対する強硬な姿勢を示したことで、会社全体でハラスメントを無くしていこうという意識が高まりました。
従業員アンケートにおいても、「以前よりも安心して働けるようになった」「困った時に相談できるようになった」といった声が増え、心理的安全性の向上が確認されました。
ハラスメントに関する相談件数も減少し、健全な職場環境が醸成されつつあります。
ストレスチェック集団分析を組織強化につなげるためのポイント
これらの事例から、ストレスチェックの集団分析結果を組織強化につなげるためには、以下の点が重要であることが分かります。
結果の深掘り
単に高ストレス者の割合を見るだけでなく、具体的な要因を特定するために、詳細な分析や従業員へのヒアリング調査を行うことが不可欠です。
経営層のコミットメント
組織強化に向けた取り組みには、経営層の理解と積極的な関与が不可欠です。
多角的な対策の実施
単一の対策だけでなく、組織の課題に合わせて複数の対策を組み合わせることが効果的です。
継続的な効果測定と改善
対策の実施後も、定期的にストレスチェックや従業員アンケートを実施し、効果を測定しながら改善を続けることが重要です。
従業員との対話
対策の実施にあたっては、従業員の意見を積極的に聞き、共に取り組む姿勢が大切です。
まとめ
ストレスチェックの集団分析は、組織が抱える潜在的な課題を可視化する貴重な機会です。
単なるデータとして終わらせるのではなく、その結果を真摯に受け止め、具体的な対策を実行できれば、従業員のウェルビーイング向上だけでなく、組織全体の活性化、生産性向上、そして持続的な成長へとつなげることができます。
事例に学び、自社の課題に合わせた組織強化の実践的なアプローチを検討していくことが、これからの企業にとって不可欠といえるでしょう。